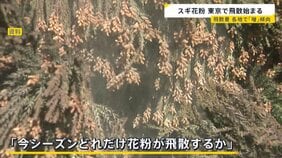ハンセン病はなぜ差別されたのか
長年、差別や偏見を受けてきた「ハンセン病」。
なぜ差別されてきたのか、法曹界はどのような役割を果たしてきたのかなどをテーマにした講演が、8月24日、「詩人 永瀬清子とハンセン病文学の読書室」(岡山市北区表町)で開かれました。
ハンセン病訴訟に関わった弁護士の井上雅雄さんが講演しました。(全3回のうち第3回)
【菊池事件】「公開の原則を無視した法廷で死刑判決 」井上雅雄弁護士が語る「ハンセン病はなぜ差別されたのか」第1回(全3回)
「鍵のかかった部屋には解剖された臓器や胎児の標本があった」井上雅雄弁護士が語る「らい予防法廃止まで」第2回(全3回)
鉈(なた)で傷を負わせた「鳥取事件」から「遺族訴訟」へ
「そうこうしているうちに、翌年の2003年にはですね、鳥取である非入所者の母親を持つ男性が、ずっとこのハンセン病問題に対しての県の動きがおかしいということで毎日のように、運動を1人で続けてた人がいまして。
その人が、その県の担当者の額に鉈(なた)で傷を負わせるという事件を起こしました。鳥取事件といいます。
そういう刑事事件があった。一審は、国選弁護人の方がもう全て認めてしまって、さらっと終わってしまったんですけども、ほとんど本人とは会っていない状態で。一審が終わって、確か懲役4年の刑が出てしまう」
「これはいかんということで、広島に在住の支援者から弁護団の方に『この事件についてちゃんと対応しなきゃいけないんじゃないか』というご意見をいただきまして。
色々議論した結果、弁護団としては、全体としてはもうちょっと性質が違う問題だということと、それからこの人が最初訴えていたのは、自分の母親を入所させなかったことがおかしいという訴え方をしてたんですね。
だから、その考え方はちょっと弁護団と相容れないっていう側面もあって、それで、刑事事件の対応は、個別の判断に任せるという形になりました」
「すると、大阪にいた神谷弁護士がやると言いまして、大阪から鳥取に行って裁判をするのは相当大変だろうなということもあって、1人に任せるわけにもいかないし。
刑事事件の時は、私と近藤弁護士の2人でやろうということになって、高裁から我々が関与するということになりました。
高裁は、松江の裁判所でずっと開かれて、全国からすごい数の嘆願書を集めてくださって、それを提出しました。
そういう中で、彼との接見も、繰り返しやって、少しずつ、関係を築いていくということをしていきました。結局少し短くなったんですけども、実刑判決で服役しています」
「2004年には、懲役3年で服役をして、その後、実はこの事件は、彼が刑を終えて出てきた時に、収入もない状況だったので、住居だけはあったんですけど、生活保護の申請をしたり、それからいろんな手続きをしたりすることを我々の方でやって、なんとか暮らせるようにという形を取っていきます。
それが、やはり彼の気持ちの中ではまだ収まっていなくて、お母さんを入所させなかったことについて争いたい、民事で争いたいというのがすごく強くなって」
「その段階で『それは無理よ』といったんですけども、どうしても納得しないので、じゃあ、裁判するんだったら、お母さんが非入所者っていうことなので、非入所者の遺族訴訟だと。
これは初めてなんですけど、非入所者訴訟と遺族訴訟は別々にあるんですけど、非入所者の遺族訴訟っていうのは初めてっていうことと、非入所者の家族の訴訟。
遺族という立場と家族という立場の両方で、家族自身の被害、あなた自身の被害と、それからその非入所者遺族の訴訟というこの2本立てでやろうかという話になって、当時大阪の神谷弁護士と近藤弁護士と私の3人で裁判を進めるということがありました」
「結局、この鳥取事件は、鳥取地裁、一審も二審も敗訴だったんですけども、一審の敗訴の時の理由として、家族にも固有の被害があるということは、一応認めたんですね。鳥取の裁判所が。
傍論でその分を認めたところがあったので、東京の赤沼弁護士とか東京の弁護団で検討した結果、家族の固有の被害を裁判すべきじゃないかという話に繋がっていきます。鳥取事件の結果が家族訴訟に繋がっているということになっていきました」