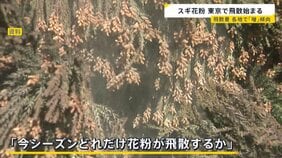療養所の将来を考える
「そうした中、やはり様々な療養所の将来の問題であったり、様々な差別偏見の問題であったり、大きな問題が残されてくる。
その残された問題をこれからちゃんと進めていくためには、基本合意だけでは不十分だということで、ハンセン病問題の解決の促進に関する法律、ハンセン病基本法と略されるんですけども、この法律を作ろうということで、我々の方で起案して国会議員の先生たちとお話をして、この法律を作っていくということが2008年にありました」
「この法律は、あるいは、その基本合意に基づいて各地で、それぞれのハンセン病療養所をどうしていくのかっていう将来構想の検討が行われるようになってきました。
岡山でもですね、長島愛生園と邑久光明園の2園合同で、ハンセン病療養所の将来構想を進める会という会議を立ち上げて、瀬戸内市長を座長として、年に3、4回の議論を継続的に進めているという状況が起きています。
これは今も続いていまして、今度市長変わりましたけども、新たな市長でどういう風に進んでいくのかなと、今見守っているところです」
「岡山の2園については、それぞれに若干違う形での将来構想っていうのができてきたんですけども、1つ外部的によく見える大きな要素としては、邑久光明園の方に、園の敷地だった場所に特別養護老人ホームを誘致したこと。
療養所にいながら社会復帰するというようなコンセプトで、そういうことも進めて、実現しています」
「愛生園の方は、外国から来た方々の研修コースみたいなのを作っていくということで、その当時は進めていくという形で、人権の教育をするための構想を練っていったという形になっています。
それがこの活動の中で、今の世界遺産登録という話が出てきて、NPOが立ち上がって、きょうの講演を主催するような運動に繋がっていっているという側面があるんじゃないかなという風に考えております」
「将来構想ができたのが2011年のことで、将来構想に従って今どのぐらい進捗しているのかみたいなことをずっと検討し続けています」