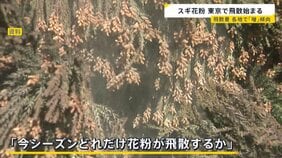補償は韓国・台湾の療養所にも適用されるのか
「2004年から2005年にかけては、全国の療養所を、国の検証会議っていう会議が回って調査をし、これまでのことを調査して、最終報告書をまとめるということがありました。
合わせて、補償法、入所歴のある方に対する補償の法律はですね、日本が統治していた時にできた韓国のソロクト更生園、台湾の楽生院の2つの療養所にも適用されるのではないかということで、韓国の弁護士さんたちと共同して弁護団を組んで、日本で裁判を行っていました」
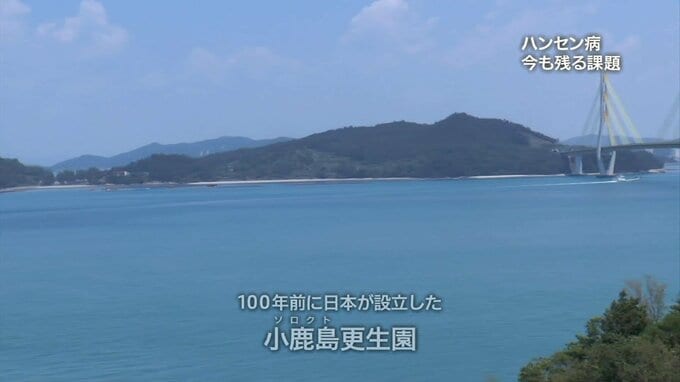
「その裁判が、2005年に同日に、午前中と午後に分かれて韓国と台湾の順で判決が出ます。韓国の判決は敗訴でした。台湾の方はですね、勝訴なんですね。
同じ日の同じ東京地裁で同じ内容について判決が真っ二つに逆の判決が出るということの、なぜなんですよね。それはね、裁判体が違うからですね。裁判長が別だった。
裁判体が違うと裁判長が別なんです。違う裁判体だったんです。裁判は自由心証主義っていう形になっているので、一方はダメ、一方は勝つっていうこともこういうケース起こりうるんですけど、まさにこの日に起こったんです」
「それで、我々はどう考えたかというと、一方は負けたけど一方は勝っている。ということは、これは結局その補償法の解釈論の問題だから、国と交渉して解釈論として認める方向にしようという運動を始めました。
それで、国会議員の先生方にも協力を受けて、結局台湾、韓国の両方の療養所の方々も含む形に補償金の法律が改正されるということで、立法的解決をはかることができました」
「韓国と台湾の裁判の時、あるいはその後もそうなんですけども、何度も、現地に赴いて、お話を伺いました。
韓国の弁護士さんたちは、本人の陳述書を作るために弁護士ではなくスタッフがやる。つまりリーガルスタッフが別にいまして、陳述書の作成は、リーガルスタッフがやることで、弁護士がやることじゃなかったんですね。
ところが、日本の弁護士は現地に行って話を聞いているので、韓国の弁護士も一緒に来てくださるようになりました。
国によって訴訟の進め方に対してのギャップがあったなと。最初は。
今、本当に親しくさせていただいてるんですけれども。そういう中で、韓国の療養者たち、それから台湾の自救会という、学生さんたちを中心とした支援者、こういった方々との関係が非常に強くなっています」