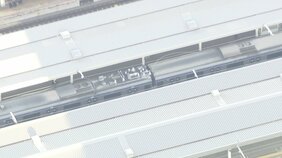◆年少者扶養控除廃止で「逆転現象」起きたまま
それが大きく変わったのは2009年。所得制限なしに中学生まで月額2万6,000円を支給する公約を掲げた旧民主党に政権交代した年です。実際は「財源不足」を理由に、半額の1万3,000円で2010年から支給が始まりました。
ただ、このとき子ども手当の支給と引き換えに、中学生以下の子育て世帯を対象とする「年少者扶養控除」も廃止されました。支給額が公約の半分になったにもかかわらず、です。結果、実はこの時から、年収が一定額を超える家庭では、手当で受け取る額より税負担が増える逆転現象が起きていました。
そして旧民主党政権末期の2012年に、所得制限が復活します。だったら年少者扶養控除も元に戻すのが筋で、実際、年末の総選挙で自民党は控除の復活を掲げて政権を奪還しますが、あれから10年たった今もそのままです。
◆老親扶養控除との整合性は?
しかも今回、児童手当の対象を高校生まで拡大するにあたって、財政当局が言っているのは「中学生以下の子育て世帯は扶養控除がないのに、高校生のいる家庭だけ扶養控除を残したら不平等になる」という理屈です。
一見なるほどと思うんですが、大きな矛盾があります。例えば「老親扶養控除」です。これは70歳以上で所得の少ない親御さんを扶養している場合に適用される控除ですが、親御さんが公的年金を受けていても年収が基準額に達しなければ控除対象になります。それが、わずか月額1万円の児童手当を支給するから扶養控除は無くすというのは、理屈が合わないですよね。
誤解しないでいただきたいのは、私は決して「老親扶養控除も失くせ」なんてことを言っているのではありません。児童手当に対してだけ、なぜ対応が厳しいのか。所得制限を復活しても年少者扶養控除は10年間も元に戻さなかったのに、所得制限なしに支給対象を広げるとなったら、即刻、高校生のいる家庭まで控除を失くすというのは、筋が通らないと思います。
◆「手当1万円」でも実質は半分以下に
では、実際に高校生の扶養控除がなくなった場合、家計にはどんな影響が出るのか、です。あくまで概算ですが、例えば夫の年収が400万円、妻が300万円で高校生の子ども1人という共働き家庭では、月額1万円の手当から、扶養控除の廃止で税金が増える分を差し引くと、残りは数千円。
つまり「月1万円支給」と言っても、実質はその半分ほどです。さらに影響が大きい専業主婦家庭で、夫の年収が700万円だと、手当から増税分を差し引くと残りは月1,000円ほど。年収900万円では、手当より増える税金の方が多くて、マイナスになります。これが高所得者への「子育て罰」と言われるゆえんです。
「でも、いっぱい稼いでいるからいいじゃないか」と思われるかもしれませんが、厚生労働省の「2021年国民生活基礎調査」によると、子育て世帯の平均年収はおよそ700万円です。先ほど言ったように、この年収だと児童手当で1万円給付されても、実質は千円から数千円程度。これで少子化に歯止めがかかるとは、到底思えません。