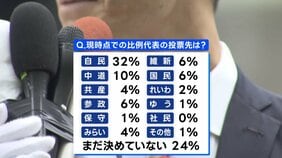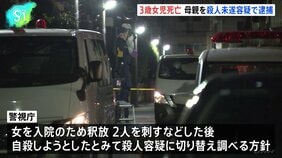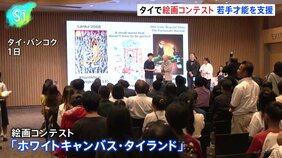◆法改正で進む学長の「独裁化」

天下りの急増など、さまざまな問題が今、大学で起きています。新書「ルポ大学崩壊」は、大学論ではなく、実際にこの10年間ぐらいで、大学で何が起こっているかを取材したルポルタージュです。採り上げられているのは、東京大学から慶応義塾大、早稲田大など大きなところもあるし、追手門学院大学、山梨学院大学、私達の近くだと福岡教育大学や下関市立大学など、26の大学についてのルポルタージュになっています。信じられないような問題がなぜこんなに起きてきているのか。それには2回の大きな法律改正があった、と田中さんは書いています。
一つは2004年。「国立大学の法人化」です。国立大学法人になったことで、国からの運営交付金が削減されていき、人件費削減、非常勤教職員の増加が顕著になってきました。大学の学長の選挙では、教職員による選挙が廃止されて、今は“意向投票”という形で投票はできるものの、最終的に学外の委員も入った「学長選考会議」が決定する仕組みに変わったんだそうです。
2004年の大きな変化では、「私立学校法の改正」もありました。学問のトップである学長や総長と、経営の長である理事長は、多くの大学で対等だったんですが、理事長を学校法人のトップに位置づけたという変化があったんです。
もう一つは10年後の2014年、「学校教育法の改正」で、教授会は学長の諮問機関に格下げされました。この法改正後も、教授会の意向を尊重した運営を続けている大学も多いんですが、国立大学の中には学長が開き直って独裁化した大学もあるそうです。びっくりしますね。私立大学の場合は、私物化を進める理事長が学長も兼務したり、時に労働法制などを無視した運営をしたりする大学も出てきています。
それから同じ2014年に「国立大学法人法」が改正されて、学長の選考方法についても「学長選考会議」が決められるようになりました。これで、学長の任期を撤廃した大学でまで出てきたそうです。“意向投票”自体を廃止する大学も出てきて、いよいよ独裁化が進む流れになってきているんだそうです。
◆「国に歯向かう人」は解任する流れに

田中:日本学術会議が、防衛装備庁のいわゆる軍事研究の予算に対して懸念を表明した後、結局ほとんどの大学は手を挙げなかったんです。手を挙げた大学は、大分大学だったり、筑波大学だったり、トップがもう人の意見も聞かない、独裁で決めてしまう大学が、いち早く乗ってしまったと。
田中:実は北海道大学の前総長が今、国と北海道大学を訴えて裁判しているんです。旧帝大で唯一、北海道大学だけが予算を取って採択されたんですけど、名和(豊春)さんが総長になって、日本学術会議の意見を尊重して、防衛装備庁予算を要らないと返した。
田中:それだけではなくて、名和さんは加計学園の獣医学部の新設にも、北海道大学として大反対だということで論陣を張ったりされていたら、ある日突然、地元の経済誌にパワハラだとか書かれた。学内の教授陣が何にも分からないところで、「学長選考会議」がパワハラで解任しようとする事態が起きた。実際、萩生田(光一)文科大臣の時に解任されたんですが、「ハラスメントは全くの事実無根である」と、今裁判をしています。
田中:独裁化が進む一方で、国の言うことを聞かないと思われる人にはこういうことが起きてしまうこと、なかなか知られていないと思っていました。今は国が『独裁をする人』を守り、『国に歯向かう人』は解任するということが、実際に起きている。
法律改正とか、日本学術会議の問題とか、一つ一つのニュースを見ているとよくわかりません。しかし、北海道大学の学長解任という、旧帝大の総長を巡って裁判で争われているのは異常なことだと言えます。
◆国の関与が制度的に強められている

そして、2021年に「国立大学法人法」がもう一回改正され、「学長選考・監察会議」と名称を変えて、権限が強化されました。文部科学大臣が任命する監事の役割が拡大され、国が監事を通して大学を間接支配することが可能になった、というのです。
神戸:政権の意向に沿わない大学トップは、解任ができる状態になっているということですね?
田中:そうです。実はこの北海道大学の総長の件があった後に、2021年に国立大学法人法を改正しているんです。「学長選考会議」を「学長選考・監察会議」という新しい名前にしまして、国=文部科学大臣が指名した監事が、総長に問題があったら会議にかけることができる、要は『国が間接支配できるようなシステム』を、北海道大学の問題が起きた後に作ってしまった。
神戸:もう制度となったたわけですね?
田中:そういう制度が、2021年にできました。
一つの方向性で学問を進めていく、研究成果を上げていくという意味で、トップダウンが必要なのかもしれません。一方で、戦争の体験があります。学術機関が戦争に協力をしてしまって、多くの人を亡くし、国が滅びる結果を招いた、という痛切な反省から「学問の自由」を戦後の大学はとても大事にしてきました。それが多分、ほとんど根底から覆されたんじゃないかなという印象を持ちました。