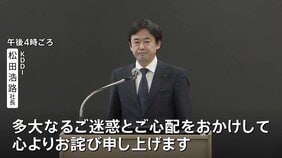歴史問題を絡める中国と外交の「あいまいさ」
さらに中国は、この問題に歴史認識を絡めようとしています。先週14日、中国外務省のスポークスマンは、高市総理の発言に関して、
「第二次大戦中、日本の軍国主義は侵略戦争を始め、人道に対する凶悪な罪を犯しました。高市総理は最近、台湾に関する露骨な挑発発言を行ない、台湾海峡への軍事介入を示唆しました。こうした日本の行動は、アジア近隣諸国や、国際社会に強い疑問と疑念を抱かせます。日本は本当に軍国主義との関係を断絶したのでしょうか?」
と述べ、第二次大戦中の日本の軍国主義と高市発言を結びつけ、アジア近隣諸国や国際社会に疑問を抱かせると主張しました。中国は、今年が戦後80周年の節目であることを利用し、日本へのプロパガンダを再び強化する姿勢を見せ始めています。
歴代総理は、台湾有事が「存立危機事態」にあたる可能性について、皆あいまいにしてきました。外交上、この「あいまいさ」は大きな意味を持ちます。米中関係や中台関係など、敏感なテーマでは、あえて白黒をつけずに「あいまい」にすることで、お互いのホンネがわかっていても納得したふりをして、落としどころを見いだすのが常套手段です。
高市総理は、自身の考えを優先し、この外交上の「あいまいさ」というカードを使わず、手の内をさらしてしまったかもしれません。この発言が、今後、日中関係の長期的な冷え込みにつながる可能性が懸念されます。
◎飯田和郎(いいだ・かずお)

1960年生まれ。毎日新聞社で記者生活をスタートし佐賀、福岡両県での勤務を経て外信部へ。北京に計2回7年間、台北に3年間、特派員として駐在した。RKB毎日放送移籍後は報道局長、解説委員長などを歴任した。2025年4月から福岡女子大学副理事長を務める