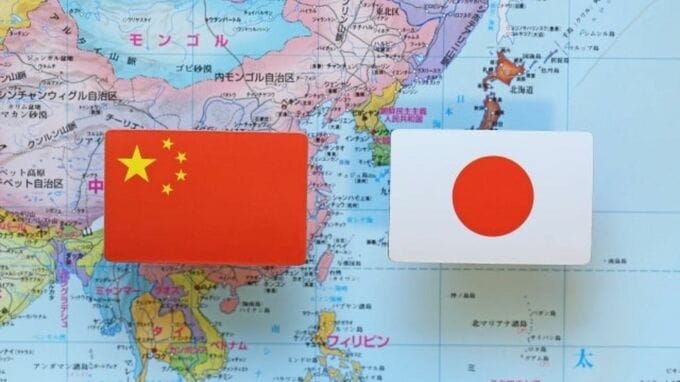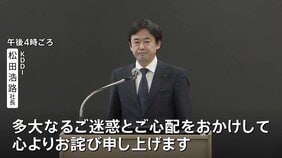高市早苗総理の「存立危機事態」に関する国会答弁が日中関係の急激な冷え込みを引き起こしています。東アジア情勢に詳しい、元RKB解説委員長で福岡女子大学副理事長の飯田和郎さんが、11月17日放送のRKBラジオ『田畑竜介 Grooooow Up』に出演し、中国側の激烈な反応の背景、そして外交上の「あいまいさ」の重要性について解説しました。
歴代政権が避けてきた「存立危機事態」の明言
高市早苗総理の国会答弁を巡り、日本と中国の関係が急速に冷え込んでいます。発端は、11月7日の衆院予算委員会での答弁です。高市総理は、台湾有事について「存立危機事態」にあたる具体例を問われ、
「戦艦を使って、武力の行使も伴うものであれば、これはどう考えても存立危機事態になりうるケースだと、私は考えます」
と述べました。「存立危機事態」とは、日本と密接な関係にある他国への武力攻撃の結果、日本の存立が脅かされ、国民の生命などが根底から覆される明白な危険が迫る事態を指し、2015年の安全保障関連法で新設されました。
歴代総理は、この「日本の存立が危ぶまれる事態」について、外交上の配慮から見解を明確にすることを避けてきました。しかし、高市総理は歴代総理として初めて、「台湾有事が存立危機事態にあたる可能性」を明言したわけです。これは、台湾有事の状況によっては、日本が集団的自衛権を行使し、自衛隊が米軍とともに武力行使に踏み切る可能性を示唆するものであり、中国に対する強いけん制となりました。