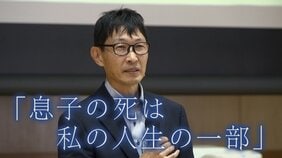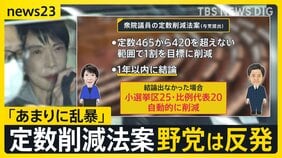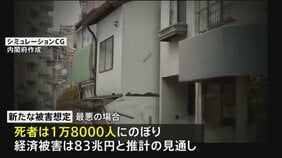シリーズ「昭和からのメッセージ」。今年は、昭和100年にあたる節目の年。当時の映像とともに昭和をひも解き、今を生きる私たちへのヒントを探ります。
8回目のテーマは「住宅団地」です。60年ほどが経過し、高度経済成長の時代に造成された鹿児島市近郊の住宅団地は現在、過疎や少子化などの岐路に立っています。昭和の時代に築いた地域の繋がりをどう受け継いでいくか考えます。
動画はYouTubeでご覧いただけます。
(記者)「鹿児島市の城山団地が見渡せる高台です。現在は住宅が密集していますが、60年ほど前は山が広がっていました」

昭和30年代から始まった高度経済成長期の人口急増の受け皿として開発が進められた住宅団地。平地が少ない鹿児島の地形もあり、鹿児島市の周辺ではシラス台地を切りひらき、昭和40年代から大規模な造成工事が相次ぎました。
昭和41年から5年かけて進められた城山団地の造成です。削り取った土砂で海岸地域の埋め立てを同時に進める「水搬送工法」による工事が全国で初めて行われました。
土砂の行き先は5キロ以上離れた現在の与次郎。完成した埋立地では、昭和47年に太陽国体が開かれました。