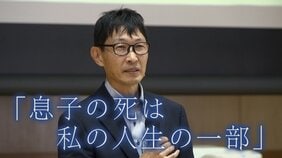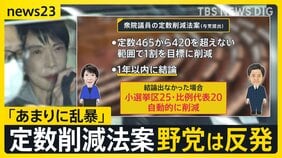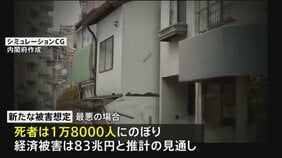シリーズ「昭和からのメッセージ」です。今年は、昭和100年にあたる節目の年。当時の映像とともに昭和をひも解き、今を生きる私たちへのヒントを探ります。
今回は、噴火を繰り返してきた霧島連山の新燃岳。災害と隣り合わせで生きる人たちの思いです。

火口から立ちのぼる噴煙。ふもとに大きな噴石が飛び、木々がなぎ倒されています。昭和34年、2月17日。霧島連山の新燃岳で江戸時代以来、137年ぶりに起きた噴火の映像です。
現在の霧島市や宮崎県の小林市や高原町に多量の噴石と火山灰が降り注ぎ、農作物などに大きな被害が出ました。
新燃岳火口からおよそ8キロ離れた霧島市霧島田口です。

佐藤春雄さん(92)と、妻のシヅコさん(91)。噴火が起きた66年前、2人は結婚して2年目でした。佐藤さん家族に被害はなかったものの、当時の様子は今でも記憶に残っています。

(佐藤春雄さん)「家からは霧島連山が全部見える。何もないところに、きのこ雲みたいにぽーっと上がって」

(妻・シヅコさん)「そのときは庭にいた。ドンといったとき。すごく上まで雲がきて怖い感じがした。もくもくしていた」