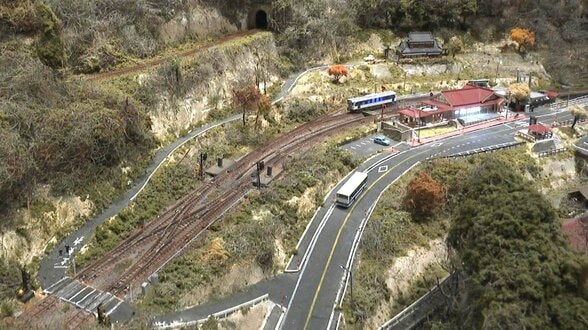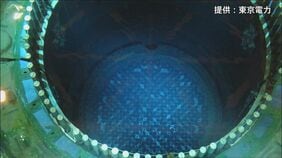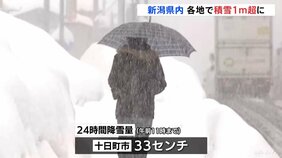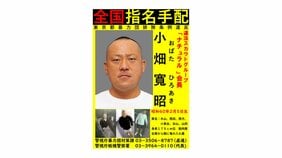花や植物にまつわるさまざまな民俗資料を集めた企画展が高知県南国市で開かれています。高知の人々と植物との文化的なつながりを知ることができます。
県立歴史民俗資料館で開かれているのは、企画展「まつりの花、いのちの木」です。
(リポート:京面龍太郎アナウンサー)
「展示室に入ると、大きな花飾りが目を惹きますね。お祭りで使うものや、死者を弔うものなど、さまざまな民俗資料が展示されています」

今月から朝の連続ドラマ「らんまん」の放送が始まったのを機に、県内に伝わる花や植物にまつわる民俗資料などが展示されています。
(県立歴史民俗資料館 梅野光興 学芸員)
「高知県の人たちと、花とか木とか、『具体的な植物』というよりは『文化的な面』でのつながりや思いを紹介する展示会」
(京面龍太郎アナウンサー)
「こちらはどういう展示物でしょうか?」

(梅野光興 学芸員)
「これは土佐市波介(はげ)で作られている『花籠(はなかご)』。波介地区の秋祭りの時にこういうものを作って、御神輿と一緒に、氏子さんがこれを手にもって御神輿についていく。御神輿についていって、最後に御旅所で氏子の人たちが花(竹ひご)を持って帰って、輪っかの形にして、玄関とか家の入口に飾って、お守りなのか魔除けなのか、そういう形で飾る習慣がある」

この「花籠」、県内では土佐市や日高村など限られた地域だけに伝わっているといいます。その形はさまざまで、土佐市波介地区に伝わるものはたくさんの竹ひごに紙の飾りが付けられています。

一方、日高村の小村(おむら)神社のものはたくさんの花飾りで彩られています。

そして、こちらの大きな絵図に描かれているのは…

(梅野光興 学芸員)
「これは吉村大我さんという方が描いた『花台(はなだい)』の絵。『花台』は江戸時代の終わりごろの高知の城下町で、お祭りの時に出てきた山車」
江戸時代の高知城下では花飾りをまとった「花台」を町ごとに作り、人々はその出来栄えを楽しんでいたといいます。
(京面龍太郎アナウンサー)
「絵を見るとけっこう大きいが、こういう大きなものが街の中を練り歩いていた?」

(梅野光興 学芸員)
「そうですね、やっぱり巨大なもの・大きいものが目を惹いて、『こんなすごいのが出たか』と。今みたいにビルとかはないので、屋根(の高さ)を超えるようなものがずっと移動してくるというのは、非常にスペクタクルというか、エンターテインメントとういか、当時の人もびっくりしたし、喜んで楽しみにして見たんじゃないか」
明治以降、まちに電線が張り巡らされると、「花台」は徐々に姿を消していきました。

その「花台」は現在、室戸市や四万十町の祭りで神輿や山車のような形で使われているほか、佐川町などでは盆踊りの時にやぐら形式のものが設置され、祭りに花を添えているといいます。

時代とともに消えたものからいまもなお存在するものまで、「花」と「植物」にまつわるさまざまな高知の文化を知ることができます。
(梅野光興 学芸員)
「知られざる高知の文化の奥深いところを味わっていただきたいのと、生活の中に具体的な植物やデザインを取り入れていくことで暮らしを豊かにしてきた高知の人たちの“足取り”の一端を感じてもらえたら」
企画展は6月18日(日)まで開かれていて、今月29日と来月3日、そして6月17日には学芸員による解説も行われます。(5月3日は入場無料)