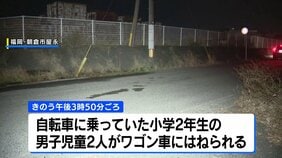戦死者の平均年齢は21歳
(元回天搭乗員 岡本恭一さん)
「8月か9月ごろに、必殺の肉弾の兵器が開発されたから、みんな希望する者は◎、まあまあ希望するのは○、希望しないものは白紙で提出しなさいと言われた。
体育館の暗幕を引いて電気をつけて、厳粛な気持ちにさせられて、そこで5分間以内に提出せよということで、友達に相談する雰囲気でもなくて〇印をかいた。そしたら搭乗員に採用された」
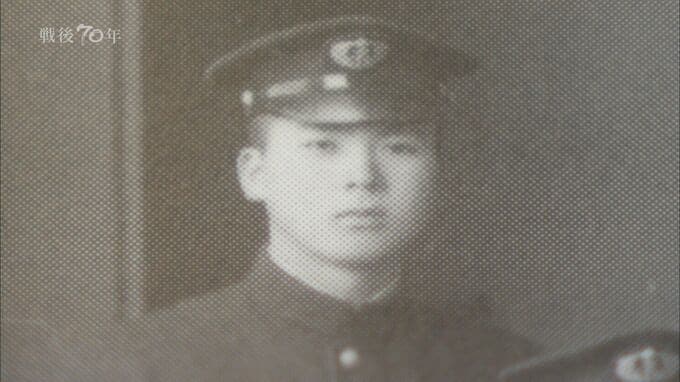
三重県四日市市で、9人兄弟の8番目に生まれた岡本さん。海軍の予科練に入り、航空兵を目指したが、戦争末期で飛行機が足りず、回天に志願した。4か月訓練を重ねたが、出撃はせず終戦を迎えた。
その後、運送会社などで働き、結婚。妻は20年以上前に他界した。なじみの喫茶店に通うのが、唯一の日課だ。

特攻兵だった事実を、家族に話したことはないという。
(元回天搭乗員 岡本恭一さん)
「家族にも回天のことを話したことはない。話しても通じないんじゃないかと思う、昔の話は」
実戦投入を急ぎ 脱出装置は付けられず

岐阜県下呂市。毎年9月、人間魚雷を生み出した、ある軍人の慰霊祭が行われている。この町に生まれ育った黒木博司少佐。回天の開発者だ。

戦争が進むにつれ空からの爆撃が戦いの中心となり、対応が遅れた日本は劣勢を強いられた。黒木は使われずに余っていた九三式魚雷を、「特攻兵器」に改造する作戦を進言。当時22歳だった。黒木は自らの血で嘆願書を書き、特攻に難色を示す上層部を説き伏せ、開発にこぎつけた。

実戦投入を急いだため、脱出装置は付けられなかった回天。黒木自身、訓練中の事故で殉職した。およそ1400人が搭乗を志願し、そのうち106人が戦死。平均年齢は21歳。特攻が失敗した場合には、自爆するよう命令されていた。