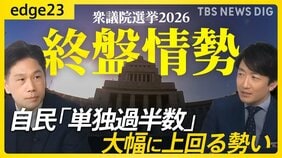能登半島地震で見直した“靴箱” 「ほとんどの靴を捨てた」
原田さん自身の防災バッグには、水を子どもと共用にする以外、自分用の荷物しか入れていません。お出かけの際、子ども用の着替えなどを入れておく「ママバッグ」とは別物なんだそうです。
エアマットは「空気で膨らませてベッドのように使うもので、体重250キロまで耐えられます。子どもと乗れます」とのこと。

<ママ用の防災バッグの中身>
□携帯浄水器
□非常用のパン
□下着
□軍手
□エアマット
□トイレセット
□タオル
□トイレットペーパー
□カイロ
□ペットボトルの水(3本)
□寝袋とアルミブランケット
□お尻拭き(手や体をふく)
□ハザードマップ
□メイク落とし
□レインコート(防寒も兼ねる)
□眼鏡
□食べ物
□歯ブラシとトイレ
□マスク
□個人情報が入ったファイル
これは1日分の避難を想定したものだそうです。
(原田さん)
「重すぎてもダメ、走って逃げられるの大きさに」
実は、能登半島地震を受けて防災バッグの中身に追加したものは、寒さ対策の「カイロ」だけ。ただ、大きく変えたことが1つあったそうです。
能登半島地震で多く見られた建物の倒壊。その様子を見て原田さんは「少しでも早く避難できるように」と、クローゼットなどにバラバラに置いてあった家族の防災バッグを、すべて玄関の靴箱に移動しました。

そのおかげで避難する動線も短くなったそう。防災バッグを入れるために「ほとんどの靴を捨てた」と笑う原田さん。最後に「一番大切なことがある」と教えてくれました。
(原田さん)
「やはり家族と話し合いが一番大切かなと思いました。それぞれが分かっていることが重要。今、この家の中で安全な場所はどこか、備蓄は何があるのか、防災バックの位置はどこか。それに、家族が離れ離れになったときは、どこに集合するのか。家族で話し合って、細かく決めました」