元日に起きた能登半島地震で、新潟市に大きな被害をもたらした液状化現象について、新潟大学が緊急調査の結果を報告し、その土地の成り立ちが原因で被害が拡大したとの見方を示しました。
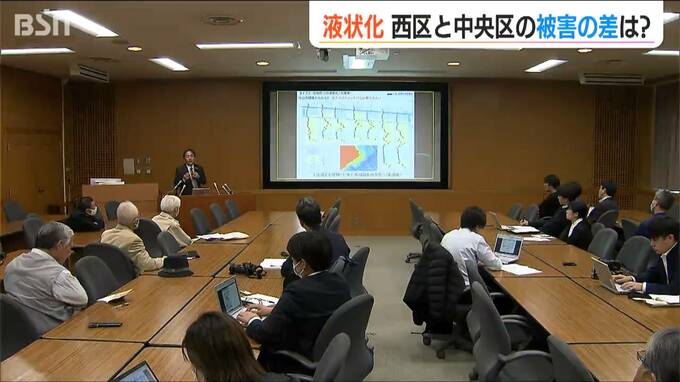
【新潟大学 災害・復興科学研究所 卜部厚志所長】
「次の世代につなぐためにどういう事が必要なのか、これが災害復旧ですのでやるしかない。これが重要」
新潟大学災害・復興科学研究所の卜部厚志所長が報告したのは、新潟市の液状化被害について行った緊急調査の結果です。
この調査は、被害が大きかった新潟市西区などで卜部所長を中心に新潟大学が独自で行いました。

寺尾地区や善久地区などで地盤の強さを測り、地層のサンプルを採取。
液状化現象がどれくらいの深さで発生したのかを調べました。

【新潟大学 災害・復興科学研究所 卜部厚志所長】
「砂なんだけど、固い地盤じゃない…」
かつて信濃川が流れていた善久やときめき西などは、およそ12mの深さまで砂の地盤だったということです。
中でも1~3mの部分の地盤がやわらかくなっていて、最も液状化がしやすい砂の細かい粒が地下水で満たされていたため、液状化現象が起きたということです。
また寺尾地区では、埋め立てに使った砂丘の砂が関係していたことがわかったということです。

【新潟大学 災害・復興科学研究所 卜部厚志所長】
「寺尾の盛り土の砂は全部均質な砂で、一番液液状化しやすい」














