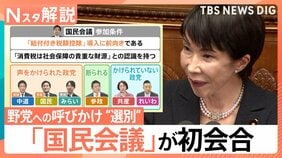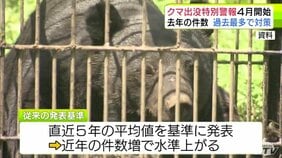日常生活や社会生活を営むのに、常に医療的ケアを受けなければならない子ども「医療的ケア児」についてです。ケア児に対応する県の指定事業所が、津軽と下北にはなく、対応が急務となっています。
検討部会には県や医療関係者など約30人が出席し、医療的ケア児の支援体制の課題を協議しました。
県内の「医療的ケア児」は24市町村で170人いるのに対し、県の指定事業所は9か所です。ただ、津軽と下北圏域では事業所はなく、地域に偏りがあります。
ほかにも、子どもが症状重い場合には事業所に預かってもらえないケースもあるといいます。
医療的ケア児がいる委員
「この子を預けないと私は治療を受けることができないのに、『母がいなくなって機能しなくなる家庭の環境はどうなのか』と(医者に)言われてしまった。緊急時に使える場所を急ぎで、なじみの病院やカルテのある所で状況に応じては受け入れを検討していただきたい」
県は、現在の9つある事業所を数年のうちに15まで増やし、家族が休息をとれるようにしたいとしています。
県障がい福祉課 千田昭裕 課長
「緊急時の受け入れの対応ができるような。また、3歳児や3歳児未満、人工呼吸器をつけている方々のレスパイト(家族の急速)が可能になるように、1日も早く受け入れ体制の整備が喫緊の課題」
県は、市町村とも連携しながら対策を強化する方針です。