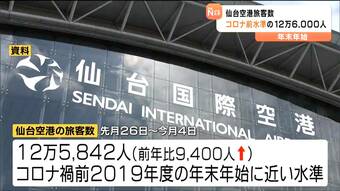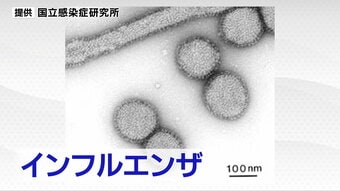宮城県女川町の離島・出島と本土を結ぶ"橋"の最後のアーチが16日、現地に架けられました。島で暮らす人々にとって、橋の完成は40年来の悲願でした。ただ、かつて1800人ほどいた島の人口はいま100人足らず。島民の思いはさまざまです。
女川町の離島、出島。こちらは、1971年の女川町・出島沖の映像です。「いけすくい」という伝統漁法で、シラスやメロウドを一網打尽にします。豊かな海に囲まれた出島は、漁船漁業で栄えました。本土との距離はわずか300メートルほど。そこに橋を架けようと1979年、期成同盟会が設立されました。今から44年前のことで国や県に要望を続けました。

しかし、一向に実現のめどが立たない中、2011年、東日本大震災が発生。ライフラインが寸断された上、一時、島民が孤立したことから橋の必要性が再認識されて、整備事業が国に採択されました。
2017年、出島架橋が着工し、40年来の悲願がようやく動き出しました。
当時の住民代表:
「本当に感無量。しけの時は船が出せないのが一番のネックだから橋がかかれば本土並みの生活ができる」
40年以上の願いが叶い、ようやくつながった本土と島。島の人たちは、さまざまな思いでその様子を見つめていました。

島民:
「避難道にもなるし、病院に行くにも時間の短縮になる。夢が今実現したからね」
島民:
「昭和40年に嫁いだんだもん『あと2,3年で橋がかかるから』と言われて。あれから何十年だもん。(孫に)出島にいないで仙台に来いと言われているけど、橋がかかるのを楽しみにしていたから。だから島に残っていた」

60年以上前は1800人ほどいた島の人口も2023年10月末現在で92人に。島には病院や商店はありません。
出島では現在、島民による団体が島の中を散策する遊歩道を整備するなど、橋の開通に向けた受け入れ態勢づくりを進めています。現在は、定期船が1日3往復、2024年12月に橋が開通すれば、いつでも町の中心部と15分ほどで行き来できるようになります。ただ、橋ができるまでの間に島の人口が大幅に減ったいま橋の開通をどのように生かすかが課題となります。