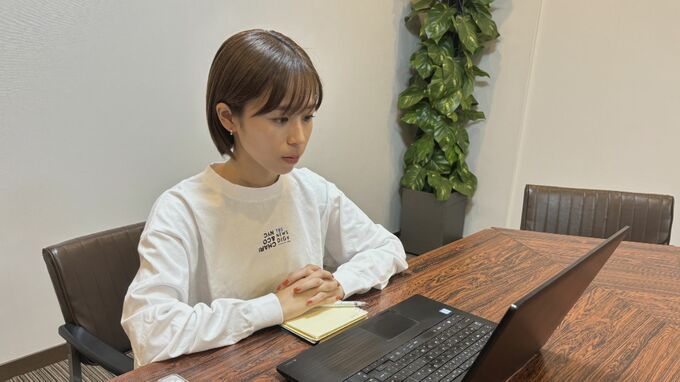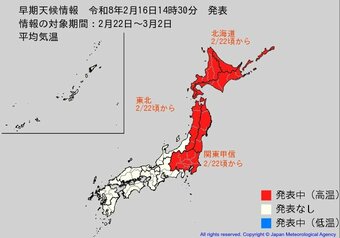東京大学大学院経済学研究科 山口慎太郎 教授:
「これは我々の研究ではないんですが、大人になってからも、30歳~34歳の年収で見てみても、早生まれと遅生まれでは、年収が4%違うということも分かっているので、完全に成長しきってからも残る違いであるということが明らかになっていと思います」
「こういった違いっていうのは、本人に全く責任がない、いつ生まれたかというのは、ほぼ偶然の産物であるわけです。そういった問題に対して、何もしないというのは、やはり不公平だろうと考えています」
山口教授は、生まれ月に配慮した入試制度などを検討すべきとした上で、教員をはじめ、教育に関わる人が意識を変えていくということも大事だと警鐘を鳴らしています。
今回の取材では、早生まれと遅生まれには、身体的な差に加えて、学力、自己効力感などの非認知能力、さらには将来の年収にまで差があるということが分かりました。
ただ、一つの学年を作るとなると、何月はじまりであっても、学年の年長と年少は存在します。クラスメイトや同じ学年の他の子どもと比べるのではなく、本人のこれまでと比べてどう変わったのかをしっかり見ていくことが重要なのかもしれません。
【取材後記】
BSS報道部のアナウンサーや記者は若手が多く、ここ数年はベビーラッシュ。先輩たちの育児トークの中で「早生まれ・遅生まれ」 という言葉がよく聞かれたこともあり、本当にそうなの?との疑問から取材を始めました。
自分自身は9月生まれということもあり、これまであまり意識したことがありませんでしたが、統計学的に生まれ月がまさかここまで影響を及ぼしているとは、正直驚きでした。
取材した山口教授によると、私立小学校などの入試では、入試の段階で生まれ月を考慮することがあるとのこと。一つの手段として、統計学的に試験点数を補正するなども考えられ、様々な子どもの事情を考慮する要素の一つとして、「生まれ月」も考えるべきだと話していました。