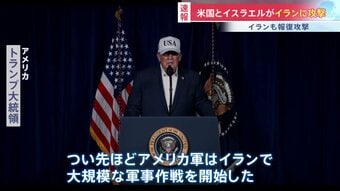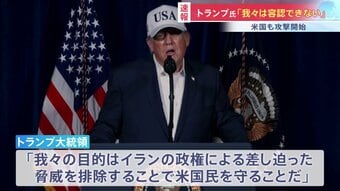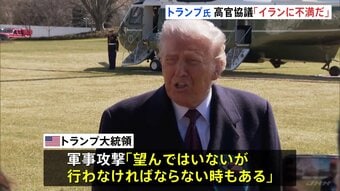信号機の「種類が豊富」が魅力!! 一体どんな違いが?
ーー種類が豊富って、信号機ってそんなにいろいろあるのですか?
「全然違うんです!製造された時代、製造したメーカー、そして、特殊な道路事情などによって変わります。
「まず、信号機は5〜10年ごとにモデルチェンジをしています。そのため年代ごとに信号機の形は定期的に変わっていっています。
また信号機の寿命は30年程度と言われており、視認性が低下した古い電球式の信号機は、どんどん新しくLED信号機へ交換されています。新しいLED信号機への更新スピードには差があり、静岡県など比較的古い電球式の信号機が、今でも残っている県もあれば東京都、福岡県、長崎県のようにほぼ全てLED信号機への交換が完了したところもあります。
いずれ近いうちに見ることができなくなるであろう古い信号機を撮影しに行くことがよくありますが、既に古い信号機が新しいLED信号機へ交換されていることもあり、その時は仕方ないといえど、ちょっとショックですね。ただ古い信号機は見づらいのも事実ですので、少しでも多く見られるうちに古い信号機をたくさん撮影したいと思っています」
ーー珍しい信号機の情報…それはどこから入ってくるんですか?
「他の方の信号機を紹介しているwebサイトや、twitterでの信号機マニアのツイート、google mapのストリートビューが主な情報源です。その情報を元にオフ会を開催して、信号機マニアで集まって見に行くこともあります」
ーーな、なるほど…。では製造メーカーの違いは何ですか?
「信号機を製造しているメーカーは、いくつもあって、それぞれの特徴を持っています。
「信号機を製造しているメーカーはいくつかあって、それぞれよく見ると特徴があります。例えば大手のコイト電工(電球式信号機製造時は小糸工業という社名)の信号機は昭和に製造された電球式のものは、透明度が高く青の色が他社に比べて濃い青色をしているのが特徴で、とても綺麗な色合いになっています」

「また日亜化学工業という大手信号機メーカーにLEDの素子を提供している企業があります。"青色"LEDを発明し、ノーベル賞を受賞した中村修二教授が勤めていた会社です。
この会社は徳島県にあり、そのこともあってか徳島県内ではLED信号機の導入・復旧が他の県に比べて非常に早く、またしばらくは他の県で普及しているLED信号機よりもLED素子が多いものを最近まで使っていました。(現在は他の県に設置されているものと同等のLED信号機を採用)」