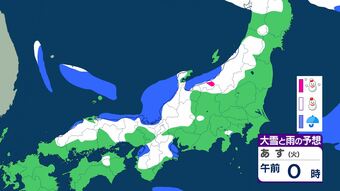結果を出さない、収容する、生活の術(すべ)を奪う
22年2月、「難民の認定をしない処分を取り消し、難民と認定する」と書かれた法相名の裁決書がAさんに渡された。あまり感情を表に出さないAさんだが、この時はニコニコしていたという。最初の申請はリーマンショックの半年前だ。難民と認められるべき人が難民と名乗り出たことが、あたかも悪いことのように扱われた14年だった。
関弁護士は振り返る。「命に関わる問題なのに、1次審査で納得のいく理由が示されず不認定になるから、ほとんどが2次審査を申し立てる。しかし、その中には入管法改正案の審議で明らかになったように、入管庁に都合のよい参与員ばかり集めた“特命門前払いチーム”に回されて書面審査だけで棄却されるケースが大量にある。Aさんの場合は、参与員が本格的な案件として資料も読み込んで対面審査し、丁寧に判断したが…」
全国難民弁護団連絡会議代表の渡辺彰悟弁護士は、「日本の難民認定の運用では、延々と結果を待たせる、収容する、生活の術(すべ)を奪うことで、申請者を送還に応じさせる行動に追い込んできた。難民を迫害の危険がある国に送り返してはならないという難民条約の原則の趣旨に反する状況が続いている」と警鐘を鳴らす。そのうえで「国際基準から見て異様に高い認定のハードルこそ本来は改善すべきだが、改定入管法は、保護されるべき人を送還する方向に舵を切り、難民が保護されない国、送還する国に向かわせようとしている」と批判する。
成立した改正法は、3回以上の難民申請者の送還を可能にしている。施行は来年とされるが、その前に難民申請者に次々と立ちはだかる壁が崩されていなければならない。