すぐに「一件落着」とはいかない
離れた場所で待つこと20分。職員2人が戻ってきました。
ーー通報があった家庭の親とは会えましたか?
子ども家庭支援センター 職員
「インターホンを押しましたが反応は無かったので、手紙を残してきました」
親は不在だったため児童相談所と子ども家庭支援センターは連名で手紙を投函。
すると親が電話に出たそうです。
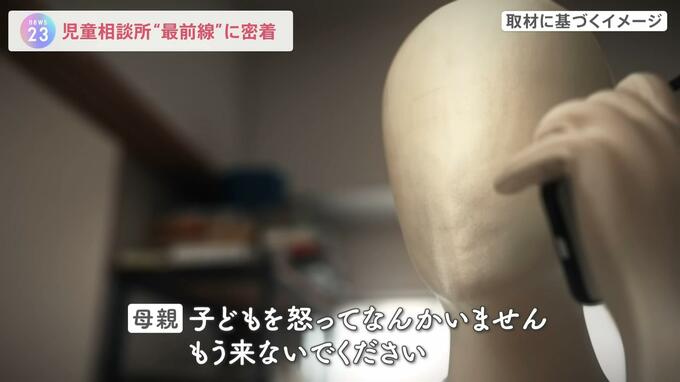
電話のやり取りの一部(※取材を基に作成)
母親:
「子どもを怒ってなんかいません!もう来ないで下さい!」
職員:
「そういうお気持ちになりますよね。連絡が入るとお話を聞かせて頂くことになっているんです。ご協力お願いします」
電話を通して感情をぶつけられましたが、職員は親との接触に成功。子どもの無事も確認できました。しかし家庭の詳しい状況はわからないまま。簡単に「一件落着」とはいきません。
児童相談所 職員
「何もなければ良いんですけど心配な気持ちは募ります。今後も継続しないといけない」
世田谷区の人口は都内最多の94万人(2023年時点)。虐待の相談件数は多い時で1か月200件を超えるそうです。区は虐待対応に加え、そもそも虐待が起きないようにする予防の取り組みに力を入れています。
過去に子どもが一時保護 虐待の“再発”防げ ―世田谷区独自の取り組み―
児童相談所 職員
「子ども家庭支援センター、児童相談所の共有ケースについて報告いたします」
この日、児童相談所と子ども家庭支援センターの職員が合同会議を開いていました。
参加しているのは北部エリアを担当する職員たちです。

実は、世田谷では区内の5エリアごとに “児相”と“子家セン”の合同チームがあります。
これは世田谷区独自の取り組み。職員同士が「顔が見える関係」になるため協力や情報共有、ちょっとした相談がしやすくなるメリットがあります。
この日、職員たちは会議が終わった後もある気がかりな家庭について話し合っていました。

この家庭では以前、母親が子どもを身体的に虐待。児童相談所が子どもを一時保護しました。つまり、危険度・緊急度は高かったということです。
その後の支援で子どもは自宅に戻ることができ、また母親と暮らし始めました。なぜ再びこの家庭が心配になったかというと、母親が妊娠したため。前回虐待が起きた原因は、育児ストレスだったからです。
児童相談所と子ども家庭支援センター職員の会話
「過去の経過から虐待が起きないのが一番だけど起きるのは心配しないといけない」
「虐待が起きた時に祖父母が子どもをみるのか公的サービスを使うのか聞ければ」
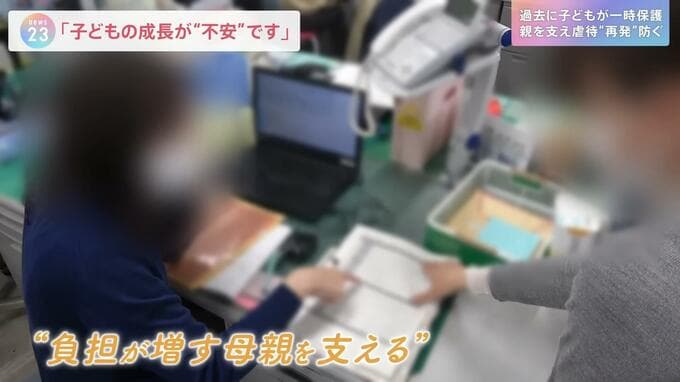
大切なのは妊娠・出産で負担が増す母親を支えること。虐待を予防するためにもサポートが専門の子ども家庭支援センターが中心となってこの家庭を支援することになりました。














