家庭訪問「子供の成長が不安です」
子ども家庭支援センター職員
「いってきます」
子ども家庭支援センターの職員が家庭訪問に向けて出発しました。
職員の右手にはバッテリー。電動自転車にセットし、ペダルを漕ぎます。飲食店が並ぶ通りを抜け、住宅街へ。
合同会議から数か月後、母親は無事に出産していました。
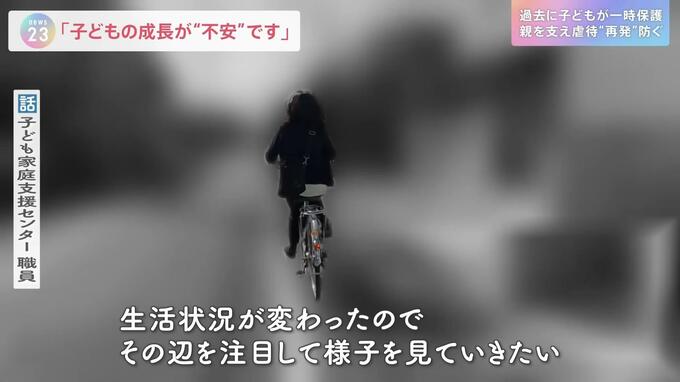
――お母さんの様子は何に注目?
子ども家庭支援センター職員
「どういう負担を感じて子育てをやられているかとか、すごく大変な思いをしていないか。生活状況が変わったので注目して様子を見たい」
20分後、訪問を終えた職員から母親とのやり取りの一部を聞きました。
職員と母親のやり取りの一部※取材を基に作成
職員:
「こんにちは。お母さん、睡眠時間は足りていますか?ご飯は作れていますか?」
母親:
「ありがとうございます。今は大丈夫です。少し余裕が出てきました」
母親は落ち着いていて、赤ちゃんと子どもも元気な様子。
行政の子育てサポートについて母親は「急ぎでは必要ない」と答えましたが、こんな言葉を口にしたそうです。

母親:
「今は落ち着いているんですけど。子供が成長していったらどんな気持ちになるか自分でもわかりません。不安です」
職員:
「またお話を聞きに来ますね。困ったらいつでも相談して下さい」
訪問後の子ども家庭支援センター職員
「今の段階では落ち着いているので現状においては良かった。ただこれからどうなっていくかは注意深く見守らないといけない」
虐待相談の対応件数は、全国で年間20万件を超えています。虐待が深刻化する前に子どもを救う。虐待そのものを防ぐ。幼い命がこぼれ落ちないよう、現場では奮闘が続いています。
最後に
虐待事件が起きる。
メディアが児童相談所を批判する。
児童相談所への不信感につながる。
また虐待事件が起きる。
この負のループを絶つ。
虐待を防ぐ責任があるのは児童相談所だけではないということが取材を通してわかってきました。
私たちメディアは、児童相談所をただ批判するのではなく、虐待が起きた家庭にどんな困難があったのか、社会にどんな支援の仕組みがあれば子どもを救えたのかという
視点を持つことが必要だと思います。
地域で暮らす大人たちは1人1人が虐待の予防策に関心を持てば救える命があるかもしれません。
全国の虐待対応件数は統計が始まってから毎年過去最多を更新しています。一度たりとも減ったことはありません。
虐待を無くすには児童相談所や子ども家庭支援センター頼みではなく私たちメディアを含め地域社会が少しずつ意識を変えることが大切だと考えています。














