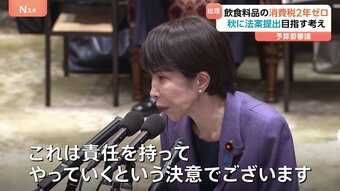今月、ウクライナ和平会議が開かれた。場所は意外にもサウジアラビア第二の都市ジッダ。
第一回の会合は6月にデンマーク・コペンハーゲンで開かれ、今回はその続きという位置づけだった。だが規模は全く違う。コペンハーゲンに集ったのは西側を中心に15か国あまり。しかし、ジッダに集まったのはロシアを除くBRICS諸国にグローバルサウスと呼ばれる国々含め40か国に上った。何故サウジアラビアが和平の中心に立ったのか…。和平のもと、繰り広げられる“実利外交”とは…。サウジアラビアを中心に戦争で浮き彫りになる国際情勢を読み解いた。
「戦後復興を考えた時…頼りになるのはサウジを中心とした湾岸諸国や投資に積極的な中国」
和平会議はもともとウクライナの呼びかけで始まった。ウクライナはここに“ロシア軍の撤退”や“領土の回復”など10項目の和平案を提案している。ウクライナにすれば、会合に参加した国々に和平案に賛同してもらい、ロシアに圧力をかける思惑があったのかもしれない。
しかし、今回、中国、UAE、エジプト、アルゼンチン、インドネシアなどが初めて参加したことでウクライナの和平案がそのまま受け入れられることもなければ、和平への道が急激に開かれたわけでもなさそうだ。ウクライナの大統領府は「大変生産的な協議を行った」と一定の評価を示した。しかし、会合に招待されなかったロシアは次のように評した。
「和平会議は無駄で失敗する運命にある努力を続けようとする西側諸国の試み。ウクライナ政権のスポンサーに常識を伝えるという意味でBRICS同胞の参加は有意義であったかもしれない」(リャブコフ外務次官)

果たして40か国と大幅に枠を広げた和平会議は、ウクライナにとっていい方向に働いたのだろうか。中東地域の専門家に聞いた。
日本エネルギー研究所 中東研究センター 坂梨祥 副センター長
「ウクライナとしてはウクライナの立場を理解して欲しいという考えがあった。ただサウジアラビアが呼び掛けたから集まった多くの国々がウクライナの立場をそのまま受け入れるかというとわからない。というのはグローバルサウスの国々はアメリカともいい関係ですが、中国とも関係がいい。今回のウクライナ戦争に関しては、どちらかというと中立な立場、そういう姿勢を維持してきた…。なのでウクライナに賛同するというよりも、そういう見方もあるだろうが、グローバルサウスとしてはこう思う…。それぞれの考えを持ち寄る会議になった。ウクライナの意図からはズレた会議だったと思う」

一方でメリットもあったというのは、在サウジアラビア日本大使館で専門調査官を務めた経験を持つサウジアラビアの研究者、高尾賢一郎氏だ。
中東調査会 高尾賢一郎 研究主幹
「戦後復興を考えた時、西側諸国がこれまでのように支援してくれるかどうか…。むしろその時頼りになるのはサウジを中心とした湾岸諸国や投資に積極的な中国といった国々ではないのか。(中略)仮に今アラブの国々が中立的、ややもすればロシア寄りだったとしても、それらの国々の協力は必要になる。そういう意味で今回の会議に成果があったかどうかは別としてサウジをはじめ、グローバルサウス、BRICSの国々と関係を維持できていることは悪い話ではない」

ウクライナにとっては当初の目的からはズレたが、別の視点では有意義だったということか。
一方40か国を集めたサウジアラビアにとっては、どんな思惑があったのだろうか…。