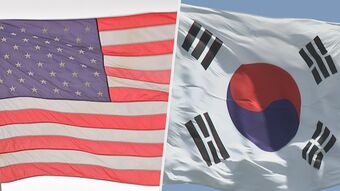8月19日に開幕する世界陸上ブダペスト大会。その最初の種目である男子20km競歩で、日本の陸上競技史上に残る快挙が実現するかもしれない。19年ドーハ大会、22年オレゴン大会とこの種目2連勝中の山西利和(27、愛知製鋼)が3連覇に挑む。前編は偉業に挑む山西の、ここまでの経験や3連覇に挑戦する心境、考え方を中心に紹介する。
世界陸上3連覇の価値は?過去の日本選手実績と比較して
山西はすでに、誰も成し得ていない偉業を達成している。日本人で2大会連続金メダルを獲得した選手は、歴史のある五輪を含めても山西しか達成していない(五輪は1896年、世界陸上は1983年が第1回大会)。
ちなみに世界陸上個人種目で2個以上のメダルを獲得したのは、以下の5人である。
千葉真子:97年・女子10000m銅、03年・マラソン銅
為末 大:01年・男子400mハードル銅、05年・銅
土佐礼子:01年・女子マラソン銀、07年・銅
室伏広治:01年・男子ハンマー投銀、03年・銅、11年・金
山西利和:19年・男子20km競歩金、22年・金
山西がブダペストで3個目のメダルを獲得すれば、室伏広治に続いて2人目の快挙となる。
個人ではなく日本チームという点で見ても、3連覇を達成すれば史上2回目である。男子三段跳で1928年アムステルダム五輪の織田幹雄、32年ロサンゼルス五輪の南部忠平、36年ベルリン五輪の田島直人で3連勝した。日本チームの連続メダルは女子マラソンが、五輪で4大会連続(92・96・00・04年)、世界陸上でも4大会連続(97・99・01・03年)で獲得している。いずれにしても個人で3大会連続(金)メダルを達成すれば、とてつもない快挙になる。
山西自身は世界陸上への抱負を「金メダルをターゲットとしながら、自分のやりたいことをキチッとできるように準備していきたい」と話した。結果も出すつもりで頑張るが、それよりも自分のやるべき中身に集中する、ということだろう。過去2回との違いを現時点でどう感じているのか。
「色んなものを一通り経験させていただいたことは、大きな違いだと思います。その上でブダペストのレースに何を求めるか。それは僕の中の感じ方なので、どう表現すべきなのか難しいのですが、僕という1人の選手が地道に泥くさく積み上げてきたものが、形になればいいかな、と思っています」
山西の言葉が何を指すのか。考察の意味も込めて書き進めたい。
2回の優勝と東京五輪の敗戦 多くのレース展開を経験済み
“一通り経験”してきたもの、の1つにレース展開がある。
19年世界陸上ドーハ大会は王凱華(29、中国)が6km付近で集団からリードを奪い、少しの間を置いた後、山西が王に追いつき、そのまま前に出て8km手前からリードを奪った。ラスト3kmのペースが想定通りにならなかったというが、残り12km強を単独歩で逃げ切った。
しかし21年東京五輪は銅メダル。17km付近でスパートしたが、M.スタノ(31、イタリア)と池田向希(25、旭化成)について来られ、18km以降で警告や注意を立て続けに出されたこともあり、3人の中で最初に後退した。金メダルのスタノから23秒差の3位に終わった。
山西は敗因を「(中盤の歩きが)あまりにも中途半端になってしまい、立ち回りに無駄が多かった」と自己分析した。王が4km手前で集団から飛び出し、5kmでは50m近くリードを許した。「王と一緒に速いペースに持ち込みたい」という気持ちと、「周りがもう少し追いかけてくれないかな」という気持ちが相半ばしていた。迷いが余分な動きとなり、力を使ってしまっていた。
10km付近から王を追い上げ2kmで約10秒を縮めたが、その間も先頭を歩いた山西が集団では一番力を使っていた。終盤の勝負どころで歩型を維持する力が残っていなかった。
その経験が山西をさらに成長させた。昨年の世界陸上オレゴンではスタートから積極的にリードした。4kmで集団に吸収されたが、集団の中で動きを整えることが目的だった。9kmから再度リードを奪い、10kmを過ぎて1kmあたり10秒以上もスピードアップした。
それでもドーハのときのように単独歩で押し切れなかった。20km競歩のトップ選手たちの力は拮抗している。16kmでは池田、S.K.ガシンバ(35、ケニア)、P.カールストロム(33、スウェーデン)が山西に追いつき4人の集団になった。
しかし山西には、追いつかれてもペースを立て直す強さが備わっていた。間もなく池田とのマッチレースに持ち込み、最後の1kmを3分41秒にまでペースを上げて池田に7秒差をつけた。22年には世界競歩チーム選手権で優勝。そのときは後半単独歩で押し切っている。東京五輪こそ勝てなかったが、19年以降の世界大会で多くのレース展開を戦い抜いてきた。