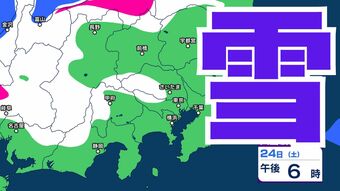「漱石の肉声を聴いてみたい」 録音された“蝋管”が、なぜ広島に?
こちら【画像①】は、円盤レコードの前身とされる記録媒体で「蝋管(ろうかん)」と呼ばれるものです。実は、日本を代表する明治の文豪・「夏目漱石」の声を録音したとされる蝋管が、広島県の旧家に保存されているんです。

ただ劣化が激しく「再生は難しい」という漱石の蝋管。どうにか声を聴けないかとRSKでは今回、所有者の協力を得て再生の手がかりを探りました。果たして漱石の声は聴くことができるのか?
かつて岡山にも1か月滞在していた夏目漱石

小説「吾輩は猫である」や「坊ちゃん」などで知られる明治の文豪・夏目漱石。漱石は岡山で暮らしていた義理の姉を訪ねて、1か月程、滞在するなど岡山でのゆかりも伝えられています。

その漱石の肉声を記録したものが、岡山県の隣・広島県内の旧家で受け継がれてきました。

(加計康晴さん)
「これが漱石先生の前にあったと思うと…何とかして再生して頂きたいですね…」
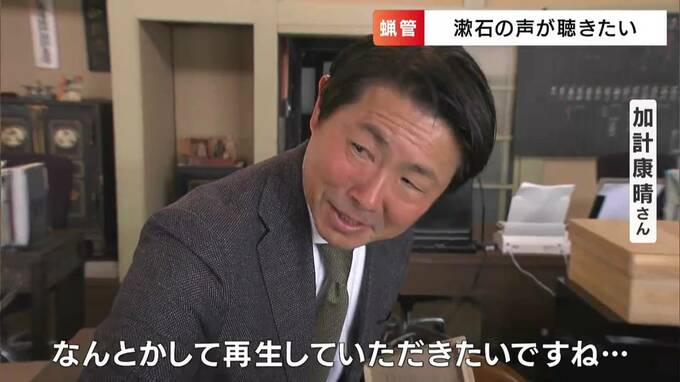
長さが約10センチの丸い筒「蝋管」。この中に「夏目漱石」の肉声が録音されていますが、残念ながら劣化が進み現在は声を聞くことができません。

「蝋管の音楽」

蝋管とは今から約150年前の1877年、アメリカの発明王・エジソンが手がけた「蓄音機」で使用する記録媒体です。蝋管は円盤レコードの前身で、初期のものは天然のロウなどを原料に作られていてます。音楽や声など収録された部分が溝として刻まれます。

漱石の声を録音したのは康晴さんの曽祖父・正文さんです。加計家は江戸時代のはじめから製鉄業や銀行業などを営んできた地元の名士で、正文さんは明治37年に東京帝国大学の英文学科に入学、漱石のもとで学んでしました。

(加計康晴さん)「(正文さんによると)漱石は非常におしゃれで面白くユーモアにあふれた人だったと。正文さんは漱石を非常に尊敬していた」

しかし、正文さんは家業を継ぐために入学した翌年、実家のある広島へと戻ることになりました。そこで、慕っていた恩師の声を、広島でも聴きたいと思い、漱石のもとを訪ね「蝋管」に声を吹き込んでもらいました。

(加計康晴さん)「どうしても漱石先生の声が聴きたいということで、蓄音機を購入して蝋管に吹き込んでもらった。ユーモアにあふれた内容が吹きこまれていたと聞いています」
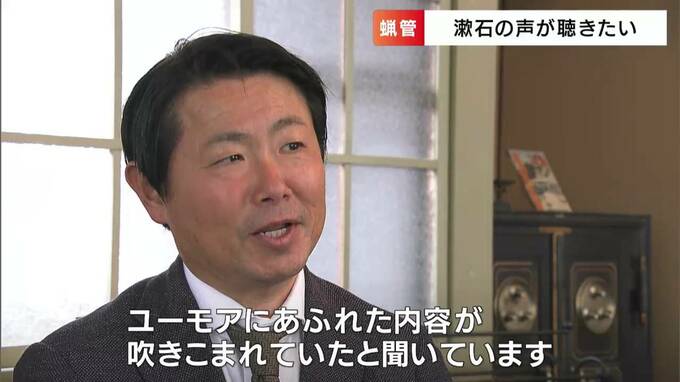
漱石の声を記録した蝋管ですが、100年以上の月日が経ちカビに浸食されるなど劣化が進み、最後に声が聴こえたのは1919年と伝えられていてます。

(加計康晴さん)「漱石先生のことが大好きだったので、何度も何度も聴いていたみたいで、長年蔵にしまっていたということで、表面が非常に傷んでいるということで中々再生は難しい聞いています」

これまでに大学の研究者が再生を試みましたが、残念ながら漱石の声を聞くことができませんでした。康晴さんのもとには当時、正文さんが所有していた「蝋管」が複数残されていますが、全て劣化が進んでいます。

画面の左が正文さんの天然のロウを主原料に作られた蝋管、一方、右が人工樹脂を主原料に作られたもので、現在も再生することが可能なものです。天然のものは、音声を記録している溝の部分を確認することが難しいことが分かります。