4年前の台風19号災害を教訓に、災害時の廃棄物やアスベスト対策について考える学習会が長野市で開かれました。
学習会は、アスベストの被害者支援に取り組む団体が開いたもので、市町村の職員などおよそ60人が参加しました。
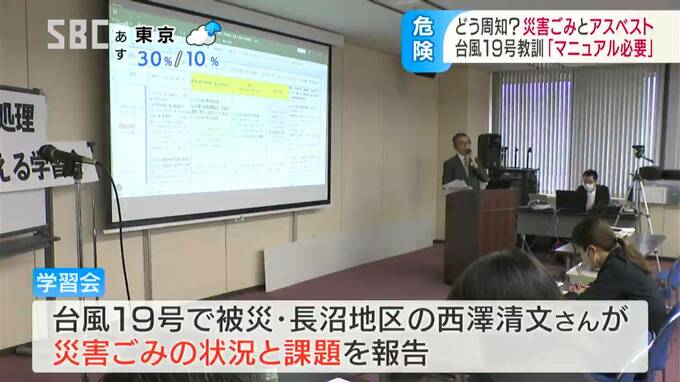
学習会では、4年前の台風19号災害で大きな被害を受けた、長野市長沼地区の元住民自治協議会長=西澤清文(にしざわ・きよふみ)さんが、災害ごみの状況と課題などについて報告しました。
千曲川の堤防決壊で多数の家屋が全壊するなど大きな被害を受けた長沼地区では膨大な量の災害廃棄物が発生し、石綿と呼ばれる「アスベスト」への対策が問題となりました。

かつて建物の断熱材などに使われていたアスベストは、肺がんや中皮腫などを発症する原因となる物質で、被災した古い建物から飛散する危険が指摘されています。
西澤さんは、当初、災害ゴミの分別の案内にアスベストへの注意喚起がされていなかったと指摘し、災害廃棄物についても初期対応のマニュアルが必要だと訴えました。
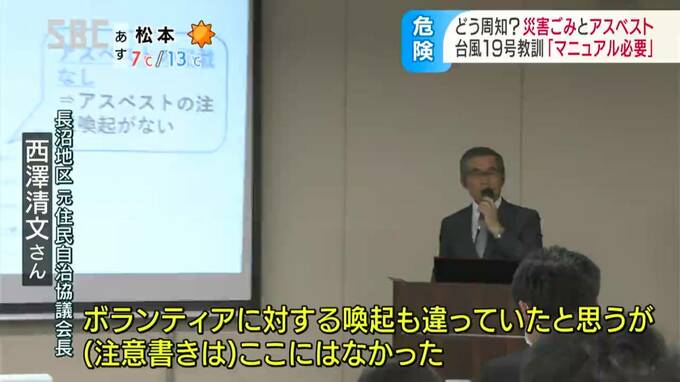
■西澤清文さん
「アスベストの『ア』でも記述があれボランティアに対する喚起も違っていたと思うが(注意書きは)ここにはなかった」
学習会では東日本大震災や熊本地震での対策も紹介され、アスベストを知らない若い世代も増える中、住民やボランティアへの周知や、解体に関わる業者への情報提供など、対策の重要性を確認しました。














