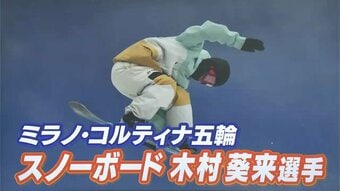恐竜研究は日々進んでいて近年、新たな事実が次々と発表されています。中でも、最先端の研究の一つとして注目されているのが「ボーンヒストロジー」です。
恐竜の骨の化石をスライスして恐竜の生態に迫る研究で、岡山理科大学生物地球学部の林昭次准教授は日本の「ボーンヒストロジー」研究のフロントランナーの1人です。(シカの映像は「新村龍也・
 研究チームは今回、恐竜研究の手法を日本に生息するシカに応用し、本島と離島に生息したシカを比べ成長の違いを明らかにしました。研究の対象は150万年以上隔離された絶滅種のシカまで含まれ、そこには、離島ならではの大型哺乳類の進化の選択が見えてきます。
研究チームは今回、恐竜研究の手法を日本に生息するシカに応用し、本島と離島に生息したシカを比べ成長の違いを明らかにしました。研究の対象は150万年以上隔離された絶滅種のシカまで含まれ、そこには、離島ならではの大型哺乳類の進化の選択が見えてきます。
研究テーマは「島に生息する哺乳類の長寿化の過程を解明する」というもので、5月22日、スイスの科学雑誌「Frontiers in Earth Science」オンライン版に掲載されました。恐竜研究の手法「ボーンヒストロジー」を野生動物の研究に応用したものとして注目されています。
発表したのは、岡山理科大学生物地球学部の林昭次准教授と東京大学大学院新領域創成科学研究科の久保麦野講師を中心とした、日本とスイスの研究チームです。
これまでも、”離島では大きい動物が小型化し、小さい動物が大型化する”という「島しょ化」という進化の法則が知られていました。また、体の大きさ以外にも、本土や大陸の同じ種の集団にない独自の特徴を持っていることも分かっています。これらの変化は、「食べ物が限られる」「天敵がいない」など、島特有の環境が影響していると考えられていますが、変化の過程や期間などは明らかになっていませんでした。
研究チームは、本土と離島の野生のシカ類(絶滅したシカを含む)の骨を調べ比較することで、「離島に長時間隔離されるほど、大人になるまでの期間が長くなり、長寿になること」が明らかになったと発表しました。今後、島に生息する小型哺乳類についても同様の分析を行うことで、さらなる島での哺乳類の進化の解明が期待されます。以下、研究の要点をまとめました。