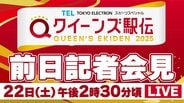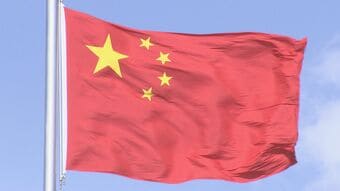日本選手権35km競歩が4月16日、石川県輪島市の1周1kmコースで開催された。男子では2時間23分13秒の日本記録で優勝した野田明宏(27、自衛隊体育学校)が、8月の世界陸上ブダペスト代表に内定。昨年の世界陸上オレゴン銀メダルの川野将虎(24、旭化成)も、ブダペスト参加標準記録(2時間29分40秒)を破り代表に内定する基準をクリアした。
野田は18年に50km競歩で日本人初の3時間40分切りを果たしたが、当時を「雑だった」と振り返る。その後、日本人競歩種目初のメダリストである谷井孝行コーチ(40)との二人三脚で、動きを洗練させてきた。その成果が輪島でどう現れたのだろう。
勝敗を分けたのは23kmからのペースアップ
野田はレース後の会見で「勝つことだけにこだわっていた」ことを強調した。すでに派遣設定記録の2時間27分30秒を突破済み。優勝すればブダペスト代表に内定するが、野田にとってはそれ以上の意味があった。
勝負を決したのは23kmからのペースアップだった。野田、川野、丸尾知司(31、愛知製鋼)の3人が1km毎4分05~06秒の周回を続けていたが、4分01~02秒まで野田がスピードを上げた。川野と丸尾も24kmまでは食い下がっていたが、25kmでは野田が約20mリードを奪っていた。
29km以降は4分05~07秒ペースに戻ったが、野田は後続との差を広げ続けて2時間23分13秒で優勝。2位の丸尾に2分36秒の大差をつけ、川野がオレゴン銀メダル時に出した2時間23分15秒の日本記録を2秒更新した。
「余裕を持っていれば後半、仕掛けてみようと思っていました。23kmから仕掛けて少し集団がばらけたので、ここかな、と一気に切り換えたんです」
23kmでペースを上げられたのは「4分05秒ペースに余裕を持つこと」ができたから。昨年の世界陸上オレゴンで9位と入賞を逃したときは、準備段階のケガの影響もあり、「先頭集団のペースに余裕度がまったくなかった」という。
谷井コーチは15年世界陸上北京大会の銅メダリストだが、11年テグ大会、13年モスクワ大会と世界陸上で2大会連続9位だった(テグ大会は失格者が出て8位に繰り上がった)。
自身の経験も踏まえ「9位の後の取り組み方次第でメダルまで行けるか、行けないかが左右されます。野田もこの1~2年が重要」と考えて指導してきた。
「競技への取り組みや考え方の緻密さが変わりました。補強のやり方など、それまではマイペースでしたが、妥協しないでより真剣に取り組むようになりました」
オレゴン後の野田は、どういった課題に力を入れてきたのだろうか。