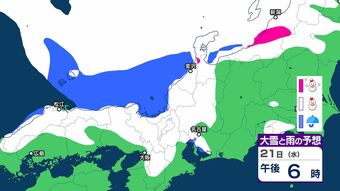「日本ブラインドサッカー協会」と言えば、文字通り、ブラインドサッカーの運営を行う団体です。今回は、同協会が一般の視覚障害者を対象に行う「同行援護」サービスに注目しました。
「同行援護」とは?
目の見えない人たちが、音の出るボールを使ってプレーする「ブラインドサッカー」は、パラリンピックの競技にもなっています。
視覚障害者の人がプレイするサッカーはもう一種類「ロービジョンフットサル」という競技もあり、こちらは弱視の人がチームを組んで、ゴールを競い合います。
「日本ブラインドサッカー協会/JBFA」はこれらの競技のリーグ戦の運営などを通じた普及を軸に、「視覚障害者と健常者が混ざり合う社会」を目指す特定非営利活動法人です。
その日本ブラインドサッカー協会が取り組む「同行援護」は、資格を持つ「ガイドヘルパー」が、視覚障害者の行きたい場所まで同行し、方向や車、歩行者、障害物の存在など移動に必要な情報を伝えるという福祉サービスです。
日本ブラインドサッカー協会では、加盟選手のトレーニングや試合会場への送迎などに限らず、一般の視覚障害者も対象に現在このサービスを提供しています。
なぜスポーツの協会が「同行援護」?
どうしてこの事業に取り組むようになったのでしょうか?
日本ブラインドサッカー協会・福祉サービスグループのサービス提供責任者である井口健司さんにお話を伺いました。
日本ブラインドサッカー協会・福祉サービスグループ 井口健司さん
「コロナ禍に於いて視覚障害の方がお困りごとがあるんだろうなというところで、日本ブラインドサッカー協会として「お助け電話相談窓口」というものを開設しました。電話等でお困り事を聞いてたんですけど、その中で外出の不便さを訴える視覚障害者の方が割りと多かったのですね。私どもが雇用している視覚障害の方も同様で、外出する際にたとえば、なかなか消毒液の場所がわからないとか、なかなか支援を受けづらいということもあって」
「協会」では元々、ブラインドサッカー関係以外の方に対しても何かサービスを提供できないかと考えていて、コロナ禍をきっかけに「同行援護」サービスを2021年4月からスタートしたということです。
アプリを作ったら利用が拡大
実はそれから1年ちょっとは利用者がほとんど居なかったのですが、去年あるツールを開発したことで、利用が広がったと言います。そのツールというのが、スマホのアプリでした。
日本ブラインドサッカー協会・福祉サービスグループ、井口健司さん
「利用者が使いたいと言っても、なかなか事業者がそれに応えてくれないと。そこを、アプリ内で何か解決できないのか?ということを考えていまして、新たなアプリを私たち独自で考えたと。それが2022年の8月ぐらいで、その辺りから徐々に利用者の方が増え始めたかなと思っています」

視覚障害者向け音声対応のこのアプリの名は「meetme-X(ミートミークス)」
利用者はこの「ミートミークス」で、同行援護を希望する日時や場所の依頼を行います。登録したガイドヘルパーの中に、そのリクエストに対し都合が合う人がいれば、両者でコミュニケーションを取って自宅や駅の改札などで待ち合わせます。その後、利用者はヘルパーと合流し、希望の場所に連れて行ってもらいます。
通常の「同行援護」サービスは、例えば毎週月曜日に午後1時から2時間といった決まった曜日決まった時間をレギュラーで利用する場合が多いのですが、この同行援護は、イレギュラーな用事でスポット的に使えるところが魅力です。他の事業者をレギュラーで契約しながら、こちらはスポットで利用という方もいるということです。
大変な「質の確保」をどうするか

このサービスを提供するためには、ガイドヘルパーが質量的にも重要です。
日本ブラインドサッカー協会・福祉サービスグループのスタッフ、上野珠美さんに聞きました。
日本ブラインドサッカー協会・福祉サービスグループ 上野珠美さん
「このガイドヘルパーは「同行援護従業者」という名前なのですが、そちらを養成する研修施設も協会で運用しています。年間に7~8回、1回あたり10人から15人あたりの募集をしていて、ガイドヘルパーも養成している状況です。その修了者が私どものガイドヘルパーになります。また、私たちの職員もその資格を取って、ガイドヘルパーとして稼働しています」
「同行援護従業者」養成研修の模様です。交互にアイマスクを着けて、視覚障がい者役とガイドヘルパー役になって行います。合わせて約20時間の講義と実技を受けることでガイドヘルパーの資格が取れます。これは無償のボランティアではなく、稼働した時間分の給与が支払われます。
全国展開への展望
この同行援護サービスには、現在20名ほどの利用者に対し、ガイドヘルパーが50名ほど登録しています。共に年齢層は、30代から60代ぐらいが多いということです。このサービスをもっともっと広げていきたいと、サービス提供責任者の井口さんは説明します。
日本ブラインドサッカー協会・福祉サービスグループ 井口健司さん
「全国にブラインドサッカーのチーム、ローヴィジョンフットサルのチームがあります。現在は東京近郊の利用が多いですけど、全国展開を想定していて、各地域各地方で使っていただく方々、もちろんガイドヘルパーもそうですし、利用する視覚障害の方も、増えていくと良いかなと考えています」
(TBSラジオ「人権TODAY」担当:松崎まこと(放送作家/映画活動家))