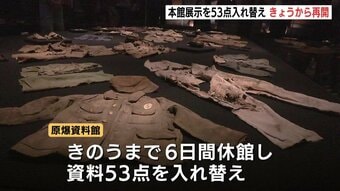誰に何ができるのか?
判決では、特に監理団体において、保護主体としての役割を実質的に果たすことが求められていたのに、彼女の腹部の変化も把握できておらず、面談は形式なものとなってしまっており、気軽に相談できる環境が整っていたとは言えず、彼女が働いていた会社との連携も十分でなかったことが指摘されました。

また、「監理団体や実習実施企業が被告人に対してもっと関心を寄せ、コミュニケーションをとることができていたならば被告人が孤立した出産を迎えることは防げたと考えられる。被告人自ら助けを求めた胎児の父親及び医療機関から助力をえられなかったのことの影響も大きい」としています。

私は、1年半に渡って合わせて20回スオンと面会しましたが、事件について聞けたことはほとんどありませんでした。関係先から話を聞くことも難しく、自分の無力さと閉塞感を味わい続けました。
しかし、取材を進めて行く中で、ベトナム人技能実習生の支援について真剣に取り組んでいる人たちと出会うことができました。全国に点在する彼らの取り組みには、光を感じました。そして彼らの中には拘置所でスオンと面会を重ねている人もいました。
執行猶予のついた判決が下り、拘置所を出た彼女に対して、私は、監理団体を通じてインタビューを申し込みました。自由の身になった彼女には、もう少し話せることが増えるのではないか、私たちがどうすれば良かったのかを、より深く、具体的に考えられるのではないかと思ったからです。
しかし、「本人が特定の支援者の方以外とは会いたくないと言っている」とのことで、依頼は断わられました。私はまたしても虚しい気持ちになりましたが、スオンにとって会いたい支援者がいる、ということには安心もしました。支援者が楽しみにしていることも聞いていました。

ところが、監理団体はすでにチケットを手配していたようで、判決の2日後には彼女はもうベトナムにいました。
本人が会いたいと言っていたはずの「特定の支援者」との夕食会が予定されていたのは、その日の夜のことでした。その人たちと会わずに帰国したことは、本人が決めたのか、それとも監理団体がそうしたのか、それは今となっては分かりません。
生まれたばかりの命が失われた今回の事件…。
彼女は、もうそっとしておいてほしいと願っているはずで、詳細が明らかになることを決して喜ばないでしょう。
それでも私は、関係者への取材や裁判を傍聴してわかったことと、そこから浮かぶ課題を、より多くの人たちと共有したいと思っています。彼女が残した言葉の意味をしっかりと受け止めるために。そして、次に生まれる子どもたちを死なせないために。
RCC中国放送/岡本幸