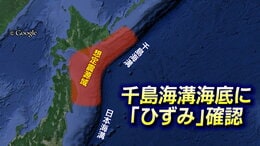世界中で読み継がれる漫画「はだしのゲン」。作者・中沢啓治さんは6歳の時、爆心地からわずか1.2キロ地点で被爆しました。実はその自伝を、「おれは見た」という短編に残しています。そこで描かれる中沢少年の凄惨な体験は後に「はだしのゲン」として描かれました。
中沢さんは語りました。
「ゲンは私そのものなんです」
ゲン=中沢少年が、「死ぬまで伝える」と決意した「地獄なんて生易しいものではない」光景、そしてあり得ない母親の死とはどれ程の出来事だったのか。「はだしのゲン」の原型である「おれは見た」をベースに番組で中沢さんが伝えたメッセージは何だったか。
TBS「筑紫哲也NEWS23」が2004年に放送した、生前の中沢さんの訴えと願いを今一度皆さんと共有したいと思います。
▼2004年8月6日OA(動画はこちらから)
▼取材・撮影・構成 TBS報道局解説委員 豊島歩
爆心地から1.2kmの光景
中沢啓治さん:
「B-29のジュラルミンが太陽に反射されてチカチカって光ってるんですよ」

1945年8月6日8時15分。
中沢啓治さんは当時小学1年生でした。
「俺は学校前でたまたま声をかけられ、偶然、塀を背にした。そのとき、光が飛び込んできた」
原爆は「ピカドン」と言われます。映画などでは「ピカッ」と光る、真っ白な閃光で表現されますが、中沢さんの眼には虹のような色で見えたそうです

「音はなかった。気づくと光を浴びたおばさんは死んでいた。町は真っ暗だった。煙がたなびいている中から、人影が見えてくるんですね」
「その人に近づいていくと、本当にびっくりしたのは…幽霊の行進がね、ズルズルと歩いてくるんですよ。水ぶくれがもう25センチぐらいの大きな水ぶくれになって、皮膚がパリッと破れるわけですね。破れると水とともに皮膚もダラダラダラダラと、水と一緒に垂れてくる。足の皮膚を引きずるとね土埃が舞い上がるんですよ」

中沢さんがまず覚えているのは、原爆投下直後は、被爆した人の悲鳴など「音がなかった」ことだそうです。
怪我をしているにもかかわらず、人々は苦しいとも痛いとも言わず黙々と歩いていたといいます。
「シーンとして。本当に音がなかったですね」
唯一聞こえた音
「ガラスが突き刺さっていましたね。一歩、歩き出すと「ジャリ、ジャリ」って。もう音が聞こえてくるんです。人に伝えるっていうことはとてもじゃないけど難しいと思います。僕の網膜に焼き付いた映像をそっくり出してみたら、どんな状態だったかはよくわかると思うんですけどね」

いったいあの日何が起きたのか。 中沢さんはこう語っていました。
”私の画にショックを受けるというけれども、私の画力ではあの程度しか書けないんです。現実はもっと悲惨だった。だから網膜に焼き付いた、頭の中の映像を出せたらいいのに、と思います”
そこで、頭の中に残る中沢さんの記憶を写真、映像資料をもとに映像化してもらいました。

中沢さんによれば、被害者で圧倒的に多かったのは、やけどを負って、ススで体が真っ黒になった人だといいます。爆風で砕けた窓ガラスの破片が刺さった人も…水のあるところには人々が傷を洗いに集まっていたそうです。
あの日…中沢さんが見た記憶をCGとして再現しました。


「地獄なんて生易しい言葉じゃないですね。現実だからね」
「俺は逃げた。おふくろも生きていたが、ショックで産気づいたのか、妹を産んでいた。町を離れ、山へ逃げた。卒倒するようなにおいが立ち込めていた。水を欲しがってね、水、水ってね。かわいそうでね」
大勢の人の死をみて 今、こう思う
「みんな生きたかったんだろうなと思うしね。人間がどういう姿に変わるかというところを伝えていかなくちゃいけないんじゃないですかね」
戦後中沢さんは原爆にこだわって絵を描き続けました。それには大きな動機がありました。
「原爆っていうのは悲惨なもんですよ。生き残っても後々まで精神的に苦しめるんですからね」
絵を描き続けた動機、それは母に起きたある出来事にありました。