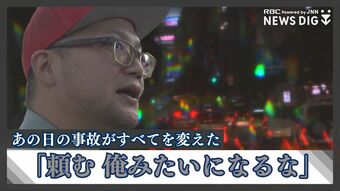沖縄では「ナーベーラー」の愛称でも親しまれている「ヘチマ」。しかし、沖縄県以外ではあまり食されていません(おいしいのに!)。
沖縄県は独自のブランドを確立し農業の発展につなげようとさまざまな農作物の新品種の育成に取り組んでいますが、このほど新たなヘチマが誕生しました!
その特徴や可能性について取材しました。

一見おなじみのヘチマに見えるこの野菜はおよそ10年かけて誕生した『美らへちま』。従来のヘチマとは違った特徴があるそうでー
県農業研究センター野菜花卉班 長浜隆市さん
「加熱しても果肉が黒くならないというのが特徴です」
さっそく違いを証明するべく従来のヘチマと『美らへちま』を同時に5分加熱するとー
従来のヘチマは、果肉の色が徐々に黒く変化していますが、『美らへちま』はご覧の通り!この黒くならない理由は、どこにあるのでしょうか?

長浜さん「従来のヘチマは酸化酵素を含んでいて、酸化酵素によって黒くなっていく、酸化していくってことなんですが、『美らへちま』はその酵素を含んでいないので、黒くならないということになります」
これまでヘチマの課題のひとつとして挙げられていた加熱時などの変色が解決されたほか、大きさや形が均一されていること、種が少なく食べやすいのも魅力のひとつで、安定した品質と収穫量を見込むことができます。
長浜さん「従来のヘチマ栽培というのは夏場に露地(屋外の畑)で栽培していて、決まった品種もなくて生産量が安定しないとか、品質が安定しないという問題がありました。これまでのヘチマに比べると、曲がりが少ない、大きさが揃っているということで、出荷した市場関係者から喜ばれているよっていうことは聞きます」
夏野菜として知られるヘチマの収穫は一般的に5月から始まりますが、『美らへちま』は冬を収穫期としていて、1年中ヘチマの流通が可能になります。

長浜さん「消費者にとっても生産者にとっても(収穫量が)安定しますので嬉しい。どちらにとってもメリットがあることになります。沖縄の温暖な気候を利用して、冬場ハウスで作ることで、ほかの県では作れない夏野菜を冬場に作れるっていうのは最大の武器ですね。」