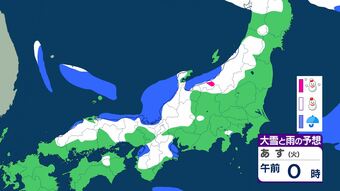国連自由権規約委員会が日本政府に「懸念」を表明
裁判では、これまでに5回、口頭弁論が開かれた。注目されるのは、原告側が、公務員の違法な行為に対する「国家賠償法」に基づくのではなく、国際法である「自由権規約」違反を根拠に賠償を求めている点だ。
原告側は「入管法の規定は、自由権規約に違反して無効で、それに基づく収容は違法」とかなり詳細に主張している。だが、法廷で傍聴している限り、国側は正面から向き合っているように見えない。入管法改正案の国会再提出を念頭に、審理を引き延ばそうとしているのではないかとすら感じる。
22年11月、原告側には、追い風とも言える動きがあった。国連の自由権規約委員会が日本政府に対して入管法に疑問を投げかける意見を出したからだ。
この中では「入管施設で収容者が死亡するという劣悪な健康状態による苦痛」「一時的に収容を解かれた『仮放免者』は働くことが認められず不安定な状況にある」「日本の難民認定率が低い」など、入管制度を巡る現状に幅広く「懸念」を表明した。
そして「収容に上限を設け、必要最小限度の期間にする」「難民を迫害のおそれがある国に送還しない」「十分な医療など収容施設の処遇改善」「『仮放免者』が収入を得る活動に従事する機会の確立」など具体的な改善点を挙げて「国際基準に基づいた包括的な庇護法」を早急に整える必要性を訴えた。
国際法は入管法より強い効力
政府が国会に再提出するという入管法改正案は、一昨年、廃案となった旧法案の骨格を維持しているとされる。
国連自由権規約委員会の意見に反して、3回以上の難民申請者を、原則として送還できるようにする“問題条項”が含まれる一方で、収容期間に上限を設定したり、「仮放免者」に就労を認めたりという改善策は何もないとみられる。「国際基準に基づいた包括的な庇護法」とは、ほど遠い内容だ。
国際人権法を専門とする明治学院大の阿部浩己教授は、「日本国憲法は、平和主義や国民主権とともに国際協調主義を打ち出しており、国際社会全体のルールである国際法は入管法より効力が強い。入管法の規定が自由権規約に抵触しているならば、その限りで無効となる」と語る。
入管法は、現在の規定に対しても、改正案に対しても、国内外から疑問符が突きつけられている。こうした問いを完全に無視したまま国会に法案が提出され、審議が進められてしまっていいのだろうか。