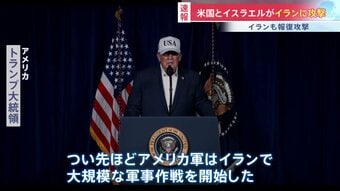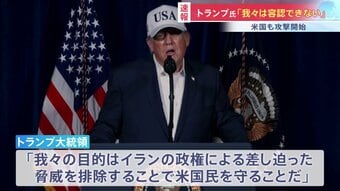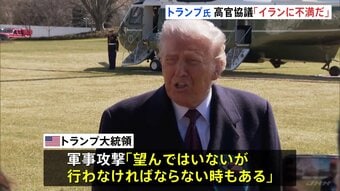■日本の閉塞感は日銀が金利を下げたり国債を買ったりして解決できる問題でない
先日公開された10年前の日銀金融政策決定会合の議事録。安倍・白川会談の翌日から行われたこの会合の議事録からは、白川総裁は安倍氏の要望に慎重だったことが伺える。しかし、1か月後の2013年1月には物価上昇目標2%導入が形式決定。さらに、これをできるだけ早期に実現することを政府と日銀の共同声明とした。

元日本銀行副総裁 西村淸彦氏
「1月の決定会合は白川さんがいわばぎりぎりやれるところまでやったということです。私としてはそこ(共同声明)までやるのかっていう気持ちでした。成果物を見た時の感覚は、半分安堵、半分不満、その二つです。不満というのは内容。内容及びそこに至る対応の仕方に不満が残ったということです。」
当時、白川総裁、西村副総裁の懸念をよそに、安倍氏は「大胆な金融緩和に向けて大きな道筋ができた」とアベノミクスの滑り出しに胸を張った。
この後、日銀総裁は黒田氏に代わり、2013年4月、“異次元の金融緩和”が始まった。
スタジオゲストのエコノミスト木内登英氏も当時金融政策決定会議に参加していた。

野村総研エグゼクティブ・エコノミスト 木内登英氏
「西村さんが辞任を考えていたっていうのは初めて聞きましたけれど…。プレッシャーが強かったのはもちろんです。衆院選前と後で雰囲気がガラッと変わった。選挙前は白川さんも毅然として、自民党の安倍総裁にも毅然として対応していた。でも自民党が予想外の大勝をした。私が言いたいのは2つ。ひとつは選挙の大勝が民意なのか…。確かに金融緩和を促すことを掲げて選挙に勝ったわけですが、それが民意なのかって…(それは疑問だが)日銀は国民生活を良くするために色々考えているけれど、選挙で選ばれていないという負い目があるんです。なので民意と言われると弱い…。(中略)もうひとつは日銀法改定をちらつかされたこと。どこを改定するのかっていうと総裁の解任権なんか有力。そうするともっと独立性が下がる。今譲歩しないともっと大変な事態になってしまう…。この2つで白川さんはじめ皆、不本意ながらも賛成したんじゃないですかね。私は最後まで賛成しなかったんですが…」
更に10年前、世の中の空気もアベノミクスを歓迎していた。
東短リサーチ チーフエコノミスト 加藤出氏
「当時は大変閉塞感が強かった。そこを打開するには思い切った金融政策、安倍さんたちが掲げたところに世論が惹きつけられたんですね。ただ当時から始まってた閉塞感というのは、金融緩和策で解決できるようなものじゃなくて、もっと構造的な問題。例えば、高齢化・人口減少化からきているものだったり、デジタル経済に日本企業が勝ち残っていけないことだったりとか・・・。日銀が金利を下げたり国債を買ったりして解決できる問題じゃなかった。しかし当時は、日銀にドカンと緩和をやらせると日本経済が復活するというのは甘い響きがあった。それで上手くいくなら痛みを伴う構造改革とかしなくていいわけですから…。」

1月30日、著名な経営者、学識者で構成される令和臨調の会見が開かれた。この10年続けた金融緩和について平野信行特別顧問はこう総括した。「金融政策に経済の構造そのものや需給全体を長期的に変えていく力があるというのは思い過ごしだった」
この産業界からの言葉から透けて見えるのは、加藤氏の言うように金融緩和の後の構造改革ができなかったことが現在の経済の停滞につながっているのではなく、金融緩和自体が産業界の緩みをもたらし、構造改革を阻んだ“原因”だったのかもしれない。