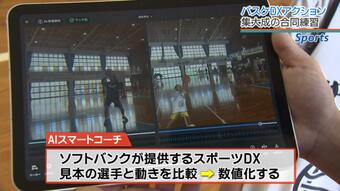時折、大胆に剪定され枝葉のほとんどが切り落とされ、丸坊主のようになった街路樹の姿が気になったことはありませんか?『強剪定』と呼ばれるこの管理方法。
樹木のダメージが大きく、枯れてしまうリスクも伴います。なぜこのような剪定をしなければならないのかその背景と解決策を考えます。

木陰をつくるだけでなく、車道沿いでは道の先のカーブをドライバーに教える視覚効果があるなど、都市で暮らす人間にとって多くの恩恵をもたらす街路樹。
しかし、沖縄では街路樹をめぐる悩ましい問題もあります。
1987年から、世界中の花木を沖縄に集めた『花の国際交流』運動によって、南米やハワイなどを中心に130万本分の種を県内各地に配付。
今では世界各地の花木が街路樹になっています。その中でもピンクや白など鮮やかな花をつけるブラジル原産のトックリキワタはその代表格ですが、手入れが行き届かず成長しすぎるものも目につきます。

造園家 武田慶信さん「3年たち4年たち、木はどんどん大きくなります。こうなると移植は難しいですからどうしても強く剪定をするしかないんですよね」
宜野湾市の県道81号。通称『ヒルズ通り』には並木道の景観が連なりますが、途中からガラッと景色が変わります。
久田記者「 奥まで木々が丸坊主ですね」
武田さん「これはね… ちょっとあり得ない」
大胆に剪定されているのは、自然環境では20mを超えるまで成長することもある、ホルトノキ。もとの樹形が分からなくなるほどの『強剪定』がされています。
通りで店を開く人が、こうなった事情を教えてくれました。

並木の周辺の店員「落ち葉が多いし木の実には虫がたかっていた。木の下には大きなアリの巣もできたみたいで、店にも入ってきた。出来ればこの木はない方がいいです」
頻繁な掃除や虫の対策に悩まされた店側が、県に対処を要望。最終的に強剪定されました。
県によると、総延長1,200kmの県道にある街路樹は10万本にのぼり、手入れがおくれては苦情が発生。強剪定が頻発しているといいます。