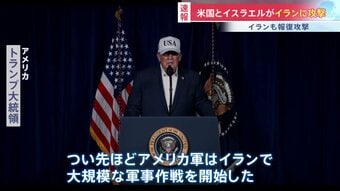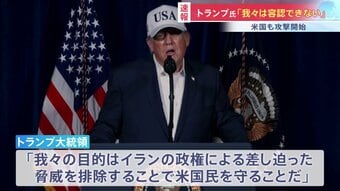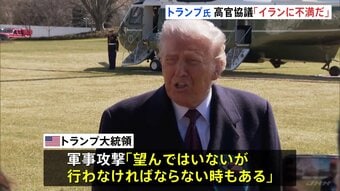■「海洋に影響力のある国と手を結ぶのが、日本が相手を選ぶ時の最優先事項だ」
“古い定義”で振り返れば日本は初めて締結した同盟はロシア帝国の膨張に備えた1902年の日英同盟だった。1921年に日英同盟が解消されて、およそ100年。新たな形で蘇った日英同盟。これは日本にとって巧くいくと語るのは自衛隊制服組のトップだった河野克俊氏だ。
前統合幕僚長 河野克俊氏
「歴史上日本には3つの同盟がある。日英同盟、日独伊三国同盟、日米同盟。これらは条約上の裏付けがあり、軍事上の取り決めがあった。私なんかはそれが同盟だって頭に入り込んでるんで(中略)3つの同盟の中で、成功したのは日英同盟と日米同盟。何かというと、やっぱり日本は海洋国家。海洋に影響力のある国と手を結ぶのが、日本が相手を選ぶ時の最優先事項だと私は思う。(中略)日独伊三国同盟はドイツもイタリアも海洋に影響力を持たなかった。それと結んでしまったから、失敗ですよね」
これには秋元氏も頷く。
英国王立防衛安全保障研究所 日本特別代表 秋元千明氏
「(同盟の場合)共通の価値観を持っていることが大事。人権を重視する、民主主義である。それから海洋国家同士のシーパワーの連携っていうのが鉄則。いわゆるランドパワーの内陸国家とは文化も違うし安全保障の概念もかなり違う」
NATOも元々は北大西洋を囲む海洋国家の同盟だった。
■「ユーラシアをまたぐ同盟は存在しなかった」
バイデン米大統領は去年『インド太平洋戦略』において、アメリカ軍だけでなく外交や経済力、同盟国など関係国の力を活用し抑止力を築くという意味で、『統合抑止力』という言葉を使った。これは今後世界の主流の考え方になっていくという。
英国王立防衛安全保障研究所 日本特別代表 秋元千明氏
「冷戦下から今日に至るまで、世界の同盟は大西洋をまたぐ同盟と太平洋をまたぐ同盟しか存在していない。ユーラシアをまたぐ同盟は存在しなかった。それがインド太平洋というのが出てきて、これはユーラシアの南側を全部押さえてるわけです。これは必要なんですよ。イギリスはそこに注目したからこそ新しいインド太平洋戦略っていうのを出してきて、空母を派遣したり、今回の日英戦闘機開発にも関心を示しているわけです。例えばTPPへの加盟申請とか、クアッドの枠組みにもイギリスは高い関心を示している。オーカスも・・・(中略)すべて統合抑止力をサポートする意味合いを持っている。イギリスはイギリスなりに日本を巻き込んで日米英で新しい枠組みをインド太平洋で築きたいという意向なんだと思います」