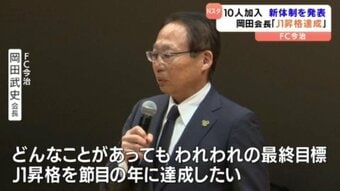あの日「日本ラグビーに愛された男」は私の目の前でこう語った。
「タックルする直前に脳裏をよぎる不安。それは痛みへの恐怖ではありません。自分の力を100%出しきれるかどうかが不安なんです」
「6万の国立」の地響きのような唸り声の中、誰よりも低く相手に突き刺さっていった紫紺の12番。
「元木由記雄」(もとき ゆきお)
日本ラグビー史上、最も敵にしたくない選手の1人である。

時間を作っていただいたのは、今から11年前の12月。神戸製鋼アドバイザーとなった元木さんは、ゆっくりとコートを脱ぎ、静かに語り始めた。
「気持ちが充実していれば、何本タックルに行っても全く平気なんです。問題は、そこまで気持ちをもっていけるかどうか。試合によってはそこまでの試合じゃない場合もある。大学選手権、日本選手権の国立ならばもう自然に気持ちも入っているんです。ただ、そこまででない試合もある。その時、どうするか。問題は全て自分自身にあるんです」
大阪工大高(現在=常翔学園)いわゆる“ダイコウダイ”の1年時には、すでにその名はラグビー界に知れ渡り、高2・高3では当然のように高校ジャパン。
そして1990年、明治の1年からレギュラーに定着すると、その後、大学日本一に3度輝いた。
「ラグビーの魅力。それは、ボールに思いがあること。ラグビーは、ただボールを横の人に回すだけではないんです。ひとりひとりの思いが、ボールに重なって回していくという競技なんです」
核心へ、言葉はパスを繋いでいく。
「痛い思いをしたヤツのお陰で、このボールが手元にある。だからミスは出来ないし、だからそいつのために『走るぞっ』と心が決まるんです」
そして、仲間の思いが結実する瞬間が訪れるという。

ラグビーから学んだこと―
「仲間を裏切らない。仲間を裏切らないというのは、体を張り続けること。自分の力を常に出し続けること。そうしないと仲間からも認められないですから」
そんな心は、さらに神戸製鋼で花開き、「骨軋むタックル」はさらに研ぎ澄まされ、積み重ねた代表キャップ「79」は当時、歴代1位。
ワールドカップ4大会連続で出場したその鈍く光る刃は、17年間に渡って味方を鼓舞し、相手を恐怖に陥れた。
「好きなんでしょうね、タックルが」
そのモトキが、一目置く存在がいた。2003年ラグビーワールドカップ。桜のジャージの12番は敗戦後、血にまみれた1人の男に目を奪われた。
「ワールドカップの時なんですが、机を叩いたらしくて。試合終わったら流血しているんですよ。僕らでさえ、そこまでいかないのに。足もケガしてたかな、もうホントにアツイ方で。でも、この人のために頑張ろうかという気にさせる方ですよ」
ワールドカップ日本代表・向井昭吾監督。人呼んで“闘将向井”

愛媛県の新田高校ラグビー部が生んだ2人目のジャパン監督だ。
2001年から代表監督を務め、その向井ジャパンの主要メンバーだったのが元木だった。
「言っている事とやっている事が一致している人。表裏の全く無い人です」
その向井昭吾監督が、選手時代の日本選手権決勝。1988年1月15日、社会人王者の東芝府中は早稲田大学に敗れた。
6万人で膨れ上がった国立に早稲田の第2部歌「荒ぶる」がこだまするのを、東芝府中のFB向井昭吾は悔しい記憶として胸に刻むのだが、その早稲田を日本一に導いた男。
それが“鬼のキモケン”
向井昭吾の先輩、新田高校ラグビー部出身の木本建治監督だ。
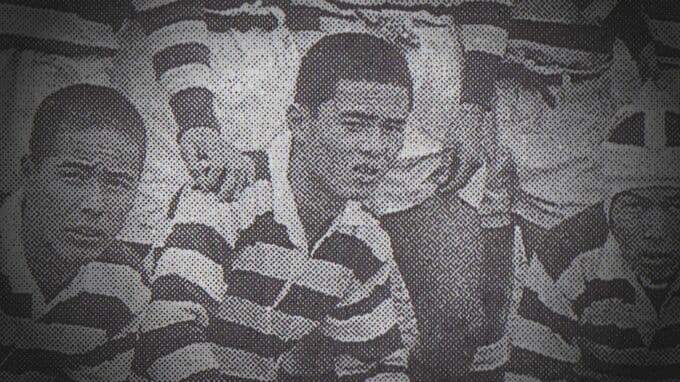
木本建治監督率いるこのシーズンの早稲田はもう1つ、日本ラグビーファンの記憶に深く刺さる名勝負を演じた。1987年12月6日「雪の早明戦」である。
前夜の雨が夜更け過ぎに雪へと変わり、決戦当日の朝、早稲田・木本監督が、永田キャプテンの電話に叫んだというその言葉は今も歴史に刻まれている。
「勝ったぞ!これは神風や!」
その木本建治監督が母校、早稲田の選手時代に遡れば自身も早明戦の歴史に名を連ねている。ただ木本のそれは試練の足跡で、早稲田の歴史で唯一2部で戦ったのが1962年「木本キャプテン」の時代だった。
ただそんな試練こそ木本には似合う。
この年、2部で全勝し1年で1部復帰を果たした“木本組”は、勢いそのままに12月2日の秩父宮での早明戦に臨み、17対8で明治を破った。
そしてここでは横の糸。
この試合の明治のナンバー8は、新田ラグビー部時代のチームメイト・烏谷忠男(元日本代表)だった。
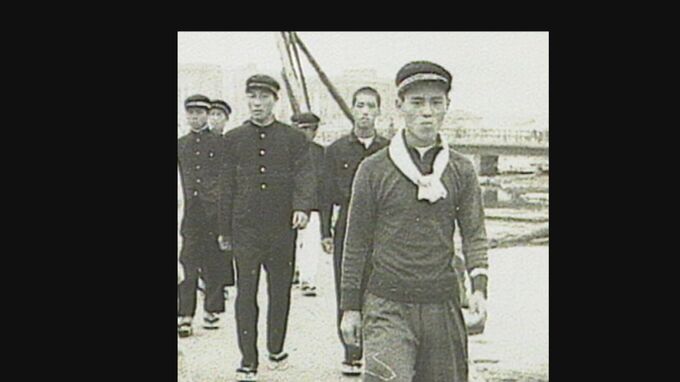
さらにその同級生対決の4年後にも早稲田では2人の愛媛人が躍動する。
7番フランカーは、松山東高校出身の和泉武雄、9番スクラムハーフは新田出身の山本巌、ともに2年生ながらアカクロを身に纏い、1966年12月4日、秩父宮で明治を破っている。
その山本巌は後にサントリー初代監督を経て1980年、82年には日本代表監督を務めている。
それは新田ラグビー部出身としては初の代表監督就任だった。
一方の和泉武雄は、後に東海大学ラグビー部の監督に就任。
「防御のタックルこそ攻撃の始まり」というアタックルの理論を進化させアタックルの上を行く一撃必殺“アタッキル”の精神を説いたと聞くが、そのヒリヒリするような指導を浴び続けてきたのが東海大学出身・向井昭吾であり、そのスピリッツは後に桜のジャージに受け継がれていくことになる。
あのモトキを唸らせ、日本ラグビーの歴史と発展の一翼を担ってきた愛媛ラグビー界の縦と横の糸。
その繊維一本一本に染み込んだ汗は、時を越えてこの冬のラガーマン達を支えうるかもしれない。