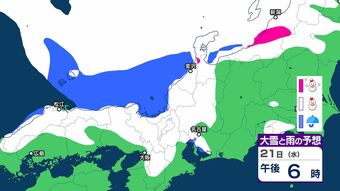「ほぼ日手帳」日本の手帳文化を世界へ
「Human Made」と同様に海外で成功を収めているのが、糸井重里率いる「ほぼ日」の手帳です。2001年から毎年発売されている「ほぼ日手帳」は2023年に累計1000万部を突破したロングセラー商品です。
注目すべきは、2025年8月期の「ほぼ日手帳 2025」の販売部数が過去最高の96万部を記録し、その売上の52.5%が海外によるものだということです。北米中米が34.1%、ヨーロッパが8.3%、中華圏が5.1%、アジアとオセアニアで4.2%と、世界の100を超える国や地域で売れています。「ほぼ日」は2025年11月にアメリカに子会社を設立するなど、海外展開を強化しています。
なぜ日本の手帳が海外でこれほど人気なのでしょうか。その理由は大きく2つあります。
1つ目は、さまざまな文化とのコラボレーションです。『ワンピース』、「たまごっち」、ホラー漫画家の伊藤潤二、テキスタイルブランド『ミナ ペルホネン』など、日本のカルチャーだけでなく、アメリカの絵本『ちいさいおうち』やフィンランド生まれの『ムーミン』など、国を超えたコラボレーションを行っています。
2つ目は、日本の「手帳」という文化そのものが海外で人気を集めていることです。「ほぼ日手帳」は英語では「TECHO」とそのまま表記され、スケジュール帳でも日記でもノートでもない、それらを兼ね備えた「ライフブック」として受け入れられています。
アメリカではマインドフルネスブームの延長で「ジャーナリング」が人気となっていますが、「ほぼ日手帳」の1日1ページの余白たっぷりのレイアウト、3.7ミリの方眼、180度開く造本、薄くて丈夫な「トモエ リバー」の用紙、そして1日1つずつ掲載された「日々の言葉」といった特徴がこのトレンドにマッチしています。
成功の共通点「ビジネスの身体化」
「Human Made」と「ほぼ日手帳」の成功には、「ビジネスの身体化」という共通点があります。これは単なるファンコミュニティの形成ではなく、ユーザーの身体的な行動や習慣と結びついた体験を提供することです。
「Human Made」では、毎週木曜日の情報公開と土曜日の発売という定期的なリズムがファンの行動パターンとなっています。新商品の情報はクラフトマンシップの独自の言葉で語られ、自発的に発信するファンコミュニティの間で流通します。
「ほぼ日手帳」は、毎日手を動かして書くことを通じて、日々の出来事を客観視する体験を提供します。ペンで書くことで得られる喜びがあってこそ、その感動を仲間に伝えたいという欲求が生まれ、自発的にファンコミュニティが形成されていきます。こうした参加の行動、体で覚えたリズムが非常に重要になってきているように思います。
ミーティングキャラバンと呼ばれるイベントでは、ニューヨークやロンドンなど海外の各都市で「ほぼ日手帳」のユーザーが集まり、手帳の使い方を見せ合います。これはPRやプロモーションというよりも、カルチャームーブメントに近い活動です。
企業はファンコミュニティをつくるよりも先に、「ビジネスの身体化」を考えるべきではないでしょうか。身体性を伴ったプロダクトやサービスは、ファンコミュニティの形成を強固にします。例えば、バンダイのガンプラは、プラモデルを組み立てる時間そのものが身体的な体験となり、強固なファンコミュニティを形成しています。
これらの企業は、単に商品やサービスを提供するだけでなく、ユーザーの行動パターンや習慣、身体的な体験と結びついたビジネスモデルを構築しています。そして、その体験を共有したいという自然な欲求から、ファンコミュニティが自発的に形成されているのです。
日本の文化を世界に売り込む上で、この「ビジネスの身体化」という視点は今後ますます重要になっていくでしょう。日本のクリエイターやビジネスパーソンがこの視点を持ち、世界に通用するビジネスを展開していくことを期待し
<コムギコ:資本主義をハックしろ!!>
毎日ニュースを100本を読むビジネス系VTuber兼リサーチャー・編集者のコムギ(comugi)が、日々の経済にまつわるニュースを解説するビデオポッドキャスト。本記事は2025年11月20日配信『ニッポンの文化を売るビジネス:「Human Made」と「ほぼ日の手帳」から「身体化」の意味を考える』から抜粋してまとめたものです。