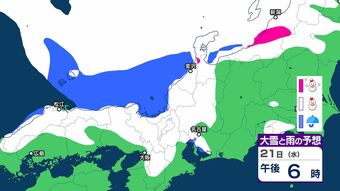専門家による支援のほか、私たちができることは?
このような専門的なスタッフによる支援も重要ですが、身近な人が犯罪被害者やその家族をどう支えるかも大事なことです。
もし、友人・知人が犯罪被害に遭ったときにはどうすればいいか?
そういう時は、相手の感情を否定せずにゆっくり話を聞くことや、普段通りに接することが大切ということです。
他の被害者と比べたり「どうして○○しなかったの?」と攻めるのはいけません。
励ますつもりで言った言葉が本人の負担になることもあります。
伊藤咲貴さんは、講演活動を続けることについてこう話します。
被害者遺族の伊藤咲貴さん
「被害者支援は本当に大変なものだと思います。
支援の仕方はさまざまで正解がなく、同じ支援をしてもその人が救われるかはわかりません。
今は講演の依頼などで被害者支援室や支援センターの方からも連絡をいただくので『やっと相談できる機関が身近にできたな』と思い、ありがたく思っています。
『講演をすることでつらい思いを思い出させてしまい申し訳ない』とアンケートに書かれる方が多くいます。
つらいという感情とはまた少し違って、私が話をすることで同じような気持ちをする被害者遺族を生まないようにしたい。
皆さんにはどうしたらそれができるかを考えてもらえたら意味があると思っています」
亡くなった人達の展示から命の大切さを考える
講演会と合わせて、国立市の会場では命の大切さを訴える展示「生命のメッセージ展」も開かれました。
飲酒運転による事故などで命を奪われた犠牲者5人の等身大パネルが並び、事故の詳細やメッセージとともに、足元には生前履いていた靴が置かれていました。

いのちのミュージアム事務局の土屋由美子さん
「新たな旅立ちとして靴を展示して、また一緒に歩いていく、生きていくということを表しています。
展示を見て、自分自身のこととして考えて欲しい。
『うちの子供と同じ年だったんだな』とか『改めて通学路を確認しました』とか、運転手さんも歩行者も両方が一緒に考える、そんなきっかけになればと思います」
こうした啓発活動を通じて、犯罪被害者への支援の輪が広がることを期待します。
(TBSラジオ「人権TODAY」担当:進藤誠人)