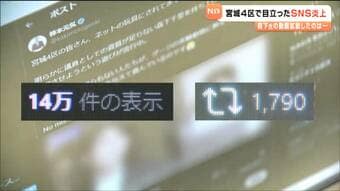一体どんな門松なのでしょうか?
江戸時代に旧仙台藩で飾られていた「仙台門松」を普及させようと、講習会が開かれました。

仙台市青葉区・青葉神社で行われた伝統的な「仙台門松」作りの実演や技術指導には、造園業者ら20人が集まり歴史や技術を学びました。

東日本大震災後に新たな資料が見つかったことを機に復元された「仙台門松」は、2本の栗の木を柱に約3メートルの松の木や笹竹を立て、門のような形にするのが特徴です。

左右の木を結ぶしめ縄の中央には「ケンダイ」と呼ばれるしめ飾りを添えます。

参加者は真剣な表情で実演の様子に見入っていました。
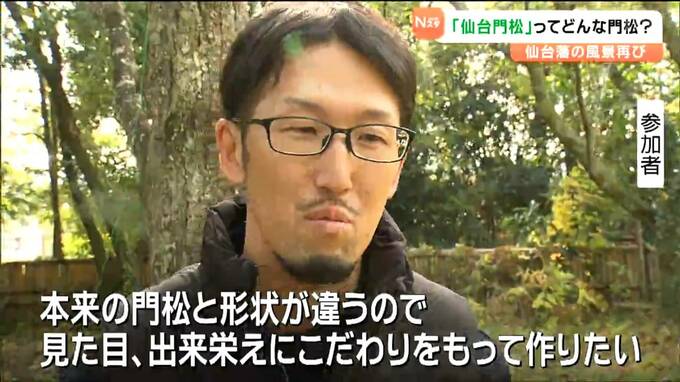
参加者:
「本来の門松と形状がちがうので、見た目、出来栄えにこだわりをもって作りたい」

参加者:
「私も三本足タイプの門松を立てるほう。ちょっとやり方は違うので参考にさせてもらいながら次回につなげたい」

「仙台門松」を復活させる活動は2020年から行われていて、主催の「仙台門松交流会」はこの講習会をきっかけに、旧仙台藩に広がった正月の風景を復活させ、まちを活性化させていきたいと話しています。