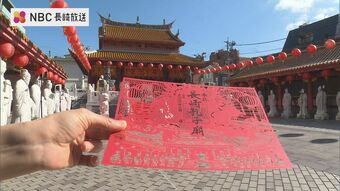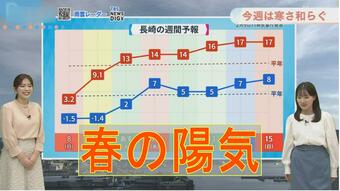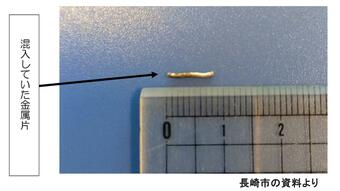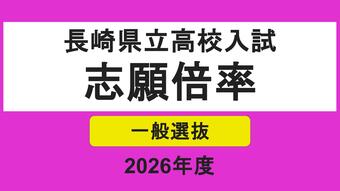長崎県教育委員会は10月29日、県内の学校における令和6年度「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」の結果を公表しました。県内の公立小・中・高校における不登校児童生徒数は4,113人で、9年連続の増加となり過去最多を更新。いじめの認知件数も2,500件と3年連続で増加しました。
不登校数「過去最多」
令和6年度、県内の公立小・中・高校の「不登校」の数は4,113人で、前年度から18人増加。これで9年連続の増加となり、過去最多を更新した。
不登校児童・生徒について把握した事案では、「生活リズムの不調(1,329人)」が最も多く「学校生活に対してやる気が出ない(1,139人)」、「不安・抑うつ(854人)」と続いた。
県教育委員会は、不登校になる要因は様々で複雑に絡み合っているケースが多いとした上で「環境の変化や学業不振、生活リズムの不調、思春期特有の心の変化や親子の問題が見られる」と分析。
また「『学校に登校する』という結果のみを目標をするのではなく、自らの進路を主体的にとらえて将来の社会的自立を目指す『教育機会確保法』の趣旨が世の中に浸透し、不登校に対する社会認識が変わってきた」としている。
※私立小・中・高校の不登校数は363人。(前年度比19人減)
いじめ件数は3年連続増加
県内の公立小・中・高校で令和6年度に認知された「いじめ」の件数は2,500件で前年比197件の増加。
コロナ禍で令和3年度まで一時減少も、翌年度から3年連続での増加となった。(最多は6年前の3,213件)
いじめの態様では「冷やかしやからかい、悪口や脅し文句、嫌なことを言われる」が1,592件(全体の63.7%)と大部分を占め、他に「軽くぶつかられたり、叩かれたり、蹴られたりする」や「仲間はずれ、集団による無視をされる」などの言動が挙げられた。
県教委は「児童生徒のコミュニケーション能力の低下や、SNSの普及によるネット上でのトラブルも増加している」と見解を発表。
一方で「いじめ認知に対する教職員の意識が高まり、アンケート調査の実施等により認知の精度が向上したことや、本人からの訴えで発覚したケースが増加した」とし、いじめの未然防止につなげていきたいとした。
※私立小・中・高校のいじめ件数は144件(前年度比54件増)
暴力行為も増加
児童生徒が起こした暴力行為の件数も増加した。
公立小・中・高校 915件(前年度比 279件増加)
※私立小・中・高校 31件 (前年度比 9件減少)
小学生では多いのは「生徒間暴力」(225件)、「対教師暴力」(106件)。生活環境の変化などによるストレスが原因となり、感情を抑えられずにふざけてぶつかる・叩く・蹴るなどの事案が確認された。