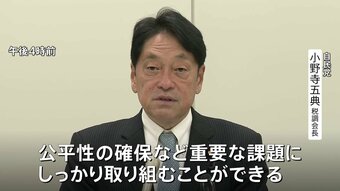安倍元総理がつくったアフリカとの国際協力スキーム
現在、日本には2万人以上のアフリカ出身者が生活しています。特に日本車の中古車輸出ビジネスを通じた関係が深く、稲場さんは「アフリカで走っている自動車の9割は日本車。日本車はアフリカでも非常に人気があり、30年以上前から、日本に中小の貿易会社を設立して、中古車や部品をアフリカに輸出する事業が続いている」といいます。
アフリカ各国との国際協力において、大きな転機となったのが、2013年に故・安倍晋三・元内閣総理大臣が打ち出した「ABEイニシアティブ」です。
※ABEイニシアティブ:アフリカの若者のための産業人材育成イニシアティブ(African Business Education Initiative for Youth)
「ABEイニシアティブ」とは、アフリカの産業人材育成と、日本とアフリカのビジネスをつなぐ人材の育成を目的として、アフリカの若者に日本の大学への留学や企業でのインターンシップの機会を提供するものです。
このプロジェクトによって多くの留学生が来日し、日本でスタートアップ企業を立ち上げるなど活躍していると稲場さんは説明します。
「日本とアフリカの人的交流の関係の幅を大きく広げたのは、安倍元総理のリーダーシップだったことをもっと知ってほしい。そして、今まで積み重ねられたアフリカと日本の関係づくりが一気に消し飛んでしまうことになると、これは非常にもったいない」と懸念を示しました。
「投資排外主義」という新たな潮流
日本で高まりを見せる排外主義には、複数の種類があると伊藤教授は分析しています。
「まずひとつは歴史修正主義による排外主義です。2000年代から在日コリアンの方を標的とする排外主義が猛威を振るっていましたが、2010年代にヘイトスピーチ対策に関する法令が整備されて下火になっていきました」
さらに、2023年からはクルド人に関する問題に見られる「福祉排外主義」が起きています。これはヨーロッパでも起きているもので、「自分たちが払っている税金や社会保険料が外国人に使われているのではないか」 という不満や反発です。
こうしたなか、伊藤教授は近年、「投資排外主義」という新たな潮流が生まれていると指摘します。
「円安政策やインバウンド政策によって、海外資本が日本に入り、中国の富裕層が日本の景勝地や水源地、タワーマンションを買い漁っているという言説が広まっている」といい、実態がそうなっていなくても、「日本はどんどん食い物にされてしまうのではないか、という不安がある」と説明します。
また、伊藤教授によれば、今回のホームタウン事業で反対運動を行った人々の中には「メガソーラー反対」という主張も見られたといいます。これは「中国資本が入ってきて日本の国土を破壊している」という懸念と結びついており、「移民反対とメガソーラー反対を掲げたデモも行われた」と述べました。
今回のような混乱は再び起こりかねない
伊藤教授の調査では、今回の反対運動には「単純に排外主義とだけ言い切れない広がり」があったといいます。
「ホームタウン事業に関しては、右派だけでなく、リベラルな市民団体や国際交流を行っている団体などからも、『考え直してほしい』という意見がありました。これまでのアフリカ各国との国際協力の積み重ねを踏まえず、トップダウンで降ってきた政策に対して、現場で活動してきた人たちが納得できないという側面があったのではないでしょうか」
また、稲場さんは「政府は、やろうと思えばまともな外国人政策、まともな多文化共生政策があればできるはずなのに、しっかりやらずに地方自治体やNPOに押し付けている。こんな状況では立ち行かなくなる」と述べました。
「『外国人政策』をもっとポジティブに、かつ多文化共生の方向性で全体的に修正していかないと、今回のような問題は何度でも起こるのではないかと思います」