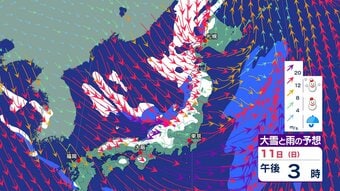戦時下、北海道の各地では厳しい監視のもと、過酷な労働を強いられる、いわゆる強制労働が進められ、朝鮮の人や日本人らの多くの命が失われました。
戦後、犠牲者の慰霊碑も建てられましたが、そうした動きが封じられたマチもありました。いったい何があったんでしょうか?
◆《雨竜ダムや鉄道建設などで約250人が命を落とす》
北海道の幌加内町朱鞠内の森に、厄を払い、幸を呼ぶための音色が響きます。朝鮮半島の伝統芸能『プンムル』です。
戦時下の強制労働の歴史を辿る『東アジア共同ワークショップ』が主催したワークショップ。日本人や韓国人ら70人ほどが参加しました。
戦時下、この地域では、過酷な労働の末、50人ほどの朝鮮人と、200人ほどの日本人が命を落としたとされています。
『笹の墓標強制労働博物館』矢嶋宰館長
「亡くなった後も、強制労働者たちはきちんと弔ってもらうことさえ、してもらえなかった」

幌加内町朱鞠内では、数千人が強制労働に動員されました。雨竜ダムの建設のほか、鉄道を開通させるため、昼夜働きづめの日々が強いられたのです。
東アジア共同ワークショップの代表を務める殿平善彦さん80歳。深川市にある寺の住職です。強制労働の犠牲者たちを弔い続け、40年以上にわたって、日韓の若者たちと遺骨を発掘し、遺族のもとに届けてきました。

東アジア共同ワークショップ代表 殿平善彦住職(80)
「いくつもの遺骨を、遺族へ届けることができたけれども、なお遺族の存在もわからぬまま、ここに置かれ続け、どこかにご遺族がいて、遺骨が帰って来るのを待っている人がいる」
強制労働の果てに命を落とし、埋葬された犠牲者。いまも故郷に戻ることなく、この地に残る遺骨があります。