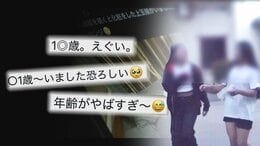防災・減災について考える「防災ウイーク」。今回は巨大地震が差し迫る北海道東部沖で進められている研究の最前線です。
7年前の9月6日、胆振地方を襲ったマグニチュード6.7の地震。

いま、これをはるかに上回る超巨大地震の発生が懸念されています。
震源域となるのは、北海道の東側、千島海溝です。
2001年以降、日本周辺で起きた64万か所にも上る地震の震源域を3Dで可視化した画像があります。

北海道東部の沖合に長く横たわる光の帯は、千島海溝周辺で引き起こされてきた地震の震源域。
海側のプレートが陸側のプレートの下に沈み込み、その境界で地震が多発しています。
千島海溝の海底で、何が起きているのか。
その謎を解明しようと8月、函館港に姿を現したのが、海洋研究開発機構=JAMSTECの研究調査船「新青丸」です。

・東北大災害科学国際研究所 富田史章助教
「これが今回の研究観測航海で設置する観測機器になります。海底に沈めたあと船から音波を出して位置を突き止めようという観測を行っている」

JAMSTECと東北大、北大の研究グループは、千島海溝沿いで海底の地殻変動の観測を続けています。

プレートの動きを明らかにし、地震を引き起こす元になる「ひずみ」のエネルギーがどれだけ蓄積されているか調べているのです。
2019年から5年間行った根室沖の観測では、プレートが毎年約8センチずつ陸側に動いていることを突き止めました。

研究グループは、巨大地震を引き起こす「ひずみ」のエネルギーはすでに蓄積されているとみていて、今回は十勝沖の2か所で新たに観測を行う予定です。

・東北大災害科学国際研究所 富田史章助教
「将来的に発生する地震リスクの評価につなげたい」

研究グループは、これらの観測データを来年春までにまとめ報告したいとしています。