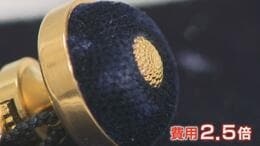「戦場とはこんな場所なんだろう」――。陸上自衛隊元幕僚長の岡部俊哉さん(66)は、当時をこう振り返る。1985年8月12日、羽田発・大阪行きの日本航空123便が群馬県の御巣鷹の尾根に墜落し520人が犠牲者となった。26歳だった岡部さんは、第一空挺団の小隊長として事故翌日に現場に降り立った。あれから長い年月が経ってもなお、岡部さんの脳裏には「焼け焦げた臭い」が焼き付いているという。当時、凄惨な現場での活動を終えた岡部さんの体には、ある異変が起きていた。

事故現場に降り立つと…「ぐにゅ」
事故翌朝の午前5時、岡部さんはいつもとは違う「命令受領ラッパ」で起床した。災害派遣に関わることだとわかると、すぐに出動準備に取り掛かった。大型ヘリのVー107に乗り込み、午前8時前に離陸。計6機のヘリのうち岡部さんは小隊長として3番機に乗っていた。
午前8時40分、「御巣鷹の尾根」の上空に到着した。ヘリからロープを使い、岡部さんは3番機から最初に降下した。JALのマークが書かれた主翼の近くに降り立ったが、その時に「ぐにゅっ」とした何かを踏んだという。その違和感の正体は人の耳だった。岡部さんはその瞬間「申し訳ありません!」と心の中で謝った。

木にぶらさがる頭皮や内臓 現場は「地獄」
山の斜面の木々は倒れ、焼け焦げた臭いがしていた。岡部さんらの任務は地形の偵察と生存者の救出で、捜索を開始したのは午前9時半頃。生存者を見つけるために「動いてください」「声だしてください」などと声かけをしながら捜索したが、目の前に広がるのは「地獄のような世界」だった。手や足の部分遺体が転がり、まともな状態の遺体はひとつもない。焼け焦げて座席と一体化してしまった遺体もあった。
「真っ赤な色をした木を触ってしまい、よく見ると肉片が付着したものでした。木の上には髪の毛がある頭皮や内蔵もぶらさがっていました。とにかく精神的に耐えられる状態ではなく『職業選択を間違えた』と思いました。」

信じられない生存者発見
そして捜索開始から約1時間が経った午前10時45分頃、無線に「生存者発見」の一報が入った。しかし岡部さんは、現場の状況をみて頭が混乱したという。人間は皆ぼろぼろなのに、なぜ転がっているぬいぐるみは綺麗な状態なのか…。「生存者発見」の一報を最初は全く信じられなかったという岡部さんは「何かの間違いじゃないか」と感じながら、生存者が運ばれてくる集合場所に向かった。子どもを含む生存者の4人は、尾根からワイヤを使ってそれぞれヘリに吊り上げて救助した。全員の救助が完了したのは午後1時半頃だった。

遺体の隣で仮眠「辛かった」
その後の岡部さんの任務は墜落現場となった尾根にヘリポートを作ることだった。人や物資の往来を円滑に進めることは自衛隊にとっても急務。ヘリポートは現場の拠点となったため、現場で見つかった遺体は次々と岡部さんがいる場所に運ばれてきたのだ。
次々と並べられていく遺体…。この夜、岡部さんはやむなく遺体の隣で仮眠をとることになったという。横になることも難しかったそうで、岡部さんは「臭いがすごくて遺体の真横で寝るのは辛かった」と厳しい表情をしながら話してくれた。8月の盆の時期。日中の暑さで遺体の腐敗が進んでいたのだろう。

「“幽霊”が窓に…」苦しんだフラッシュバック
岡部さんは事故発生から3日後の15日の朝に現場を離れたが、それまでずっと仮眠は遺体の横が定位置だったという。岡部さんは御巣鷹山での任務を振り返る。
「現場に入った直後はショックが大きかったものの、翌日には『大丈夫だ。俺はやっていける』などといった“慣れ”を感じている自分がいました」
当時は感染症の概念も薄かったのか、遺体を素手で触ることにも抵抗はなかったという。しかし任務を終えて、帰宅してから3日ほど経った時、岡部さんの体にある異変が起き始めた。
夜になると、御巣鷹山の現場で見たり触ったりした遺体が幽霊のようになって窓の外に並ぶようになった。日中や深夜の訓練では問題ないのに、帰宅して部屋に一人でいると症状が出る。
「とにかく暗い場所が嫌で、トイレ、風呂、台所など全ての部屋の電気を付けていました」
さらに臭いも敏感になっていて、肉も食べられない。一人で寝ようとするとフラッシュバックが起きるため、毎晩のようにウイスキーを飲んで、無理やり寝ていたという。