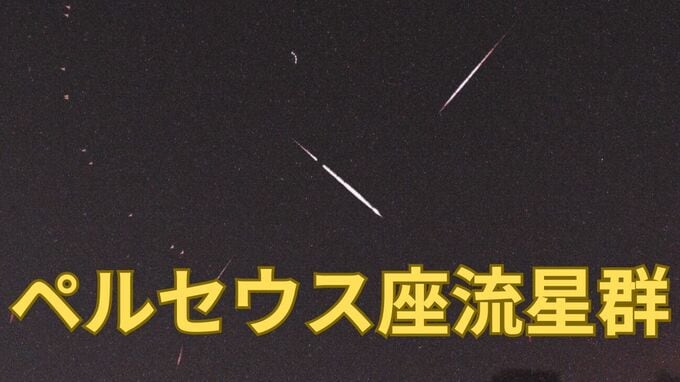ペルセウス座流星群が今年も見頃を迎えます。
月明かりとの“駆け引き”がカギ
毎年8月13日前後、地球はスイフト・タットル彗星が残した軌道を通過します。この際、彗星が撒き散らした微細なチリが地球の大気に飛び込み、流星として夜空に現れるのです。これが「ペルセウス座流星群」として知られる現象です。
天文学に詳しい岡山市中区の山陽学園大学地域マネジメント学部の米田瑞生さんに、今年の特徴や観察のポイントをききました。
ー今年は、よく見られそうでしょうか。
(山陽学園大学 米田瑞生さん)
「今年は8月13日未明に活動が最も活発になると予想されています。つまり、12日夜に夜更かしをすれば、多くの流星に出会えるチャンスがあるということ。
ただし、ひとつ注意点があります。今年は12日20時半ごろに月が昇り、一晩中、明るい月明かりが空を照らします。これにより暗い流星は見えにくくなるため、観察の際には月明かりを背にするなど、見る方向を工夫することが重要になります」
ーどちらの方角を見たらよいでしょうか。
「本来、ペルセウス座流星群は東の空、ペルセウス座の方向から流れるように見える流星群ですが、今年は方角よりも『月を避ける』ことがポイントになるかもしれません。
とはいえ、ペルセウス座流星群は活動期間が比較的長いのが特徴です。極大(ピーク)を迎える前後、たとえば月明かりの少ない7月下旬や8月下旬も、流星を観察するには意外と良いチャンスです」