戦後80年プロジェクト「つなぐ、つながる」です。およそ2000人の命が奪われた静岡空襲の犠牲者を悼む日米合同慰霊祭が先日、行われました。かつての敵国同士が共に祈りを捧げる貴重な場ですが、いま、大きな転機に差し掛かっています。
今月21日、静岡市葵区で開かれた日米合同慰霊祭。地元の人や在日アメリカ軍の関係者らおよそ200人が80年前の静岡空襲の犠牲者を悼みました。
1945年の6月20日にかけて起きた静岡空襲では、市民およそ2000人が犠牲になったほか、空中で衝突したアメリカ軍のB29の搭乗員23人が亡くなりました。
日米双方の犠牲者を悼む慰霊碑の前で執り行われるセレモニーを半世紀以上にわたり主催してきたのが、医師の菅野寛也さん(91)です。
静岡市出身の菅野さんは、小学6年生の時に静岡空襲を経験しました。B29の墜落現場で見た搭乗員の遺体は忘れられないといいます。
菅野寛也さん
「(遺体の)背中だけ見ました。何秒か見てるうちに、『こいつらも犠牲者だ、かわいそうだな』と」
軍医だった祖父に教えられたのは「敵兵を看護する医者になれ」。菅野さんが子どものころに受けた強烈な体験と教訓がいまの日米合同慰霊祭につながっているのです。
ただ、この慰霊祭は現在、大きな問題に直面しています。
菅野寛也さん
「この会を続けるのは難しくなってきた。慰霊の火というのは消したくない」
慰霊祭の会場は小高い山の上。91歳の菅野さんにとって、暑い中、1時間半の登山は体力的に相当な負担です。
菅野寛也さん
「やっぱりきついね。楽じゃないよ」
また、菅野さんは慰霊祭の運営に私財を投じてきました。次の世代に引き継ぐためには、こうした問題を解決しなければなりません。
それでも、世界中で紛争が相次ぐいまだからこそ、合同慰霊祭を続けるべきだと菅野さんは強調します。
菅野寛也さん
「世界各地でこういうことができれば、戦争なんか起こるはずがないと思う」
「サンキューベリーマッチ」
最後に交わした握手は平和への約束。参列者の姿や振る舞いは世界へのメッセージです。
注目の記事
「価格破壊の店」「市民の味方」物価高続く中”10円焼き鳥”守り続ける店主の思い 創業75年の老舗居酒屋 福岡・大牟田市

20歳の娘は同級生に強姦され、殺害された…「顔が紫色になって、そこで眠っていました」 女子高専生殺害事件 母親が語ったこと【前編】

障がい者就労支援で疑惑「数十億円規模」の給付金を過大請求か 元職員が語った加算制度の悪用手口「6か月ごとに契約だけ切り替えて...」 事業所の元利用者も"高すぎる給付金額"に不信感
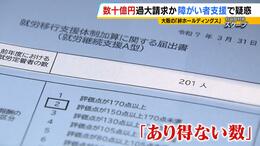
「拾った小石で竹に落書き」「立ち入り禁止エリアに侵入」京都の人気スポット・竹林の小径で迷惑行為が深刻化...記者の直撃にも悪びれないインバウンド客たち 地元商店街からも嘆き「本当にやめてもらいたい」

“ニセ警察官”から記者に詐欺電話「保険が不正使用されている」だまされたふり続けると“事情聴取”も…【特殊詐欺手口の全貌】
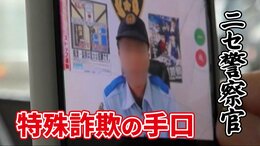
15年前の“時効撤廃”なければ逮捕されることはなかった 安福久美子容疑者(69) 別事件の遺族は「ぱっと明るくなりました」 全国には未だに350件以上の未解決事件









