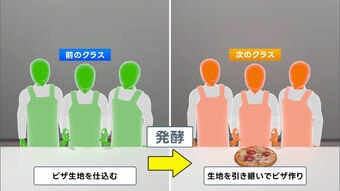6月7日と8日、沖縄県・宮古島南方で中国の戦闘機J-15が海上自衛隊のP-3C哨戒機に対し、2日連続で異常接近するという事態が発生した。2機の距離はわずか45mにまで縮まり、極めて危険な状況だったといえる。東アジア情勢に詳しい、元RKB解説委員長で福岡女子大学副理事長の飯田和郎さんが6月16日放送のRKBラジオ『田畑竜介 Grooooow Up』に出演し、この異常接近事件を深掘りし、中国の空母と戦闘機、そしてその意外な「ルーツ」について解説した。
危険な異常接近と中国側の反論
今回の異常接近は、海上自衛隊のP-3C哨戒機が、太平洋を航行していた中国の航空母艦「山東」を監視していた際に起こりました。P-3Cの翼幅が30.4m、J-15の翼幅が約15mであることを考えると、45mという距離がいかに間近であったか想像に難くありません。まさに翼幅2機分に相当するスペースで高速飛行していたことになります。
この危険な行動に対し、中国外務省のスポークスマンは、日本側の防衛省による公表の翌日、「中国の正常な軍事活動に対して行う、至近距離での偵察はリスクとなる。我々は危険な行為をやめるよう、日本側に求める」と反論しました。つまり、「日本が悪い」という主張です。
P-3Cは哨戒機であり、その任務は主に海上で敵の警戒に当たること。中国外務省が言う「至近距離での偵察」とは、海自のP-3Cが空母「山東」を監視していたことを指します。中国側は、自らの空母への監視を妨害するため、J-15を異常接近させたというわけです。
過去にもあった異常接近と接触事故
軍用機が他国の航空機に異常接近するケースは、過去にも発生しています。2014年8月には、南シナ海を巡航飛行していたアメリカ軍の哨戒機に対し、中国の戦闘機がわずか6mまで接近した事例があります。この海域は中国南部、海南島から200kmほどの場所であり、中国側の「ウチの庭先に入るな」という意図があったと推測されます。
さらに深刻なのは、接触事故に至ったケースです。2001年4月、やはり南シナ海の上空でアメリカ海軍の偵察機と中国の戦闘機が空中で接触。米軍の偵察機は海南島に緊急着陸したものの、中国の戦闘機は墜落し、乗員と機体は海中に消えました。
この事故は中国国内で猛烈な反米感情を高め、緊急着陸した米兵24名が中国側に身柄を拘束されるという事態に発展。米中間の交渉の末、彼らが帰国できたのは、緊急着陸から12日後のことでした。
異常接近は、時にパイロット個人の「腕比べ」のような精神状態から生じることもある、と航空自衛隊の元パイロットは推測しています。相手の搭乗員の顔や表情まではっきり見える距離まで接近し、過去には表情やポーズで挑発するケースもあったといいます。