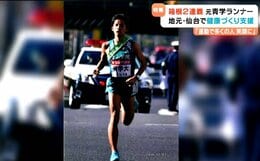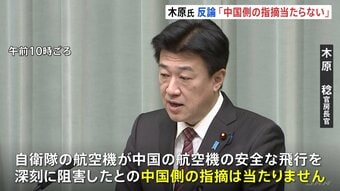子どもの自殺をどのように予防するか
ここまでの分析を手掛かりに、子どもの自殺をどのように予防すべきか、いくつかのアイデアがみえてくる。
絶対に子どもの自殺を止めたいのであれば、第一の方法として、子どものスマートフォンの所持、SNSの利用、OTCの販売を制限し、高層建物や駅には飛び降り・飛び込み防止の物理的対策を講じるべきである。しかし、今日の社会状況でこのような対策を徹底することは経済的・政策的に困難であろう。
第二の方法として、自殺手段に関するセンセーショナルなメディア報道は、可能な限り自制し、より前向きなメッセージを表現するべきだろう。
子どもは、無意識に他者の影響を受ける被暗示性が高く、共感する子どもの自殺がセンセーショナルに自殺手段とともに報じられれば、社会的学習によってその行動を容易に模倣する。オーバードーズの歌が巷に流行り、女子高生の自殺の案件が具体的にネットで報じられれば、情報は数千倍に拡散して、子どもの自殺を増やす。
現在学校で実施されているスマートフォン利用を含むインターネットリテラシー教育には、自殺に関連する有害情報への対応項目がない。欧米では、SNSを使う子どももメディア発信者であるとして、ネット上で利用者が死にたくなった時に行うこと、友人に死にたいといわれた時の対応など、自殺予防の手法を教える教育が始まっているという。
第三に、自殺未遂者の再企図防止や、子どものうつ病の早期発見・早期治療に本腰を入れる必要がある。
このためには、絶対数の少ない児童精神科医やカウンセラーの養成拡充、子どもの自殺予防の多職種チームの編成など、医療と行政に予算をつけて機動的な支援体制を整備していくこと、また家庭や学校で大人が子どもたちと積極的なコミュニケーションをとり、孤立・孤独にある子どもたちの声を聴くスキルを身につけることが必要である。
子ども向けにSOSの出し方教育や、タブレット型端末やSNSの相談窓口を支援する試みも盛んではあるが、精神科臨床で出会う死にたい子どもの多くは、親や教師など、そもそも身近な周囲の大人に気持ちを話す時間をもらえないことや、話しても理解してもらえないこと、関係をあきらめていることを訴える。
今や親の共働きが当然の家庭で、学校不適応から不登校となった子どもは、誰もいない家でゲームをし、適切な支援がなければ孤立するほかはない。これらの子どもに我々が実施することは、本人の話を真剣に聴き、大人と子どもの、あるいは子ども同士のつながりをほぐし、彼らの居場所を考えることだが、これには大変な時間と労力がかかる。一度傷ついた子どもの心を回復させるのは、専門家でも容易ではない。
現在、「自殺対策基本法の一部を改正する法律」案が厚生労働委員長から提出されており、子どもに関わる自殺対策に社会全体で取り組むこと、学校が責務として子どもの自殺に取り組むこと、心の健康教育と啓発の推進、自殺未遂者への医療支援体制整備、自治体での関連機関協議会設置、子ども家庭庁の所掌業務としての位置づけなどが提案されていると聞く。
しかし、子どもの自殺が増加しているという事実は、サン・テグジュペリの「星の王子様」に書かれているように、小手先の大人の対策が子どもの自殺予防には無効であること、子どもの目線からみた生きるための想像力が、自殺予防に必要なことを示している。
<執筆者略歴>
太刀川 弘和(たちかわ・ひろかず)
1967年生。1993年筑波大学医学専門学群卒業、博士(医学)。筑波大学附属病院、茨城県精神保健福祉センター、茨城県立友部病院、筑波大学保健管理センターを経て、2019年より筑波大学医学医療系臨床医学域災害・地域精神医学教授
青年期精神医学、災害精神医学、自殺予防学が専門。様々な時事問題に隠れるメンタルヘルスの諸相を、個人と社会の相互関係から考察する。茨城県災害・地域精神医学研究センター部長、日本自殺予防学会理事も務める。
著書に「つながりからみた自殺予防」(人文書院)など。
【調査情報デジタル】
1958年創刊のTBSの情報誌「調査情報」を引き継いだデジタル版のWebマガジン(TBSメディア総研発行)。テレビ、メディア等に関する多彩な論考と情報を掲載。原則、毎週土曜日午前中に2本程度の記事を公開・配信している。