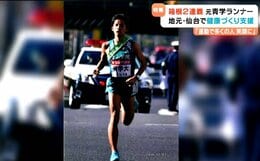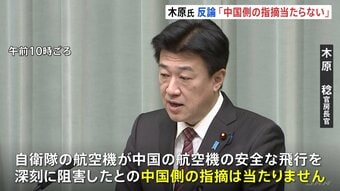子どもの自殺はなぜ増えたのか
しかし、動機の統計は、一人につき4つまで計上しており、個人の自殺の動機としてどれが強い影響といえるのか延べ数ではわからないことに加え、動機不明も一定数おり、経年的には各動機の比率に変化は少ないため、近年の子どもの自殺増加の関連要因を説明するには不十分である。
前項の子どもの自殺の原因・動機の分布は、病気はうつ病、児童期は家庭問題、思春期は学校、友人問題が関連するという、従来の研究の指摘とあまり大きくは変わらない。
一方、ある集団の自殺が急激に増加する場合は、動機に加え、新たな自殺の手段や自殺につながる行動が増えることが報告されている。
例えば、かつて東アジアの練炭自殺、東南アジアの農薬自殺、エストニアのウォッカ乱用などが、自殺者数増加の主な要因となり、これらの販売を制限して自殺が減少したことがわかっている。近年の子どもに関して言えば、過量服薬(オーバードーズ)や自傷行為(リストカット)の増加が指摘されている。
そこで、厚生労働省のデータに加え、警察庁集計による自殺の手段、経済産業省によるOTC医薬品(薬局や薬店で処方箋なしで購入できる医薬品)販売額、文部科学省の「児童生徒の問題行動に関する調査」における、いじめ重大事態発生件数、小中高校生の不登校件数、ならびに総務省の「情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査」におけるスマートフォン利用率について、平成26年から令和6年までの時系列データを収集し、10代の男女別自殺者数の推移と比較した。

結果は表1の通りである。この表では自殺との関連が疑われる指標を行ごとに示し、列に性別の自殺者数との相関係数、解釈を記載している。相関係数とは、ある数字が同じ時期の数字とどの程度関係しているかを示す指標で、片方の指標が増えればもう片方も増えるという関係を示し、係数が1に近づくほど相関が高い。
まず、OTC医薬品の年間販売額の増加は女性の自殺者数増加とのみ有意に相関していた。いじめ重大事態の年間件数の増加は、女性の自殺者数増加と強く相関していた。小中学生の不登校者数の増加は、男女の自殺者数と相関しており、特に女性の自殺者数増加と強い相関を認めた。高校生の不登校者数増加は男女とも自殺者数推移と有意な相関はなかった。
スマートフォンの利用率増加は男女とも自殺者数増加と有意に相関していた。自殺未遂歴増加は女性の自殺者数の増加と強く相関していた。
ただし、ここでいう相関とは、統計学的に同時に数が変化しているという意味で、必ずしも直接の原因を意味しているわけではないことに注意を要する。
子どもの自殺はなぜおこるか
自殺を予防するためには、自殺リスクを上げる危険因子を減らし、リスクを下げる保護因子を増やすことが重要とされる。
子どもの自殺の危険因子には、精神疾患、自殺企図歴、自傷歴、孤立、家族背景(家族の自殺歴、家族関係の不和、虐待体験)、ネガティブなライフイベント(学校不適応、いじめ、喪失体験)、メディアの影響(報道、SNS、アニメ)があげられている。また自殺の保護因子には、家族のつながりの強さ、学校での良好な対人関係があげられている。
さらに、アメリカのジョイナー博士が提唱している自殺の対人関係理論では、人は、「自分が周りに迷惑をかけている」という自己負担感の増大と「自分が孤立している」という自己所属感の減弱があれば自殺願望が高まり、これに自殺する能力や手段が加われば自殺行動が生じるという。
今回の分析結果にこれらの学説を適用すると、近年の子ども、特に女子は家族関係、学校の対人関係のストレスからうつになって自己負担感を生じやすく、また小中学校で不登校となり、孤立すれば孤独感、すなわち自己所属感の減弱も生じやすい。
このような中でスマートフォンの利用は、SNSなどを通して飛び降りやオーバードーズの情報を容易に入手し、具体的に模倣できる。いじめや自殺未遂の増加に周囲の大人たちが十分対応できなければ、不幸な結末が増える。こうして、子どもの自殺が増えているのではなかろうか。