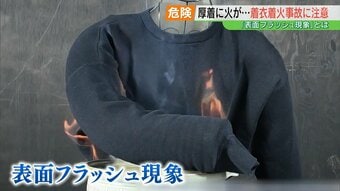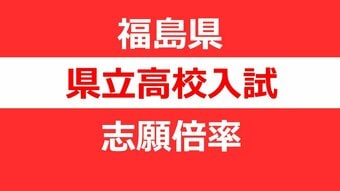寺は「住民が集う場」
心のよりどころだった長安寺の再建に、住民も期待を寄せています。津島から茨城県に避難している三瓶忠良さん。墓が長安寺にあります。

三瓶忠良さん「その辺の空き地になっているところは全部(墓を)持って行った人なんだよね。でもやっぱりうちは先祖代々、ここにあったんで。ここに作ったわけ」
寺は、先祖を供養する場であるとともに、住民が集う場所でもあったと三瓶さんは話します。
三瓶さん「震災になってもやっぱり春と秋の彼岸にはみんなここに来て、で、しばらくだねってことでね。やっぱりみんな、集う場所だったんですよね。これで3年後に本堂が目に見えてね、建てばやっぱりまたみんなの考え方がね…。これから、長安寺がここにあったっていうことがわからない世代の人も、ああ、ここかと。ここにあったんですかということがね。目に見えてわかるんで」
境内の一角で穴を掘っているのは、今野幸四郎さんです。避難先の本宮市の自宅や津島にサクラの木を植えている今野さん。地鎮式を記念し、自分で育てたサクラの木を境内に植えました。

今野幸四郎さん「ようやくここへきて、地鎮式ができましたんで、これからいつでも来れるなって、そんなふうに思っています。まあ、(震災から)十何年にもなったからね、若い人はわかんないんだよな。昔のことも、前のことも。14年前のことをわかんねえ人もいるから、だから、それでも、こういうよりどころがあって、ここに本堂ができれば、みなさんとともにな、元気を励まして、暮らしたいなと思いでいます」
再建に向けた一歩を踏み出した、長安寺。本堂の完成は、3年後を目指しています。完成後も、福島市の別院は残し、2つの拠点で寺を運営することにしています。
30代の横山さん。今後について、悩むこともありますが、住民とともに歩んできた、歴代の住職たちの姿を思い描きながら、進んでいきます。
「住民に慕われ続けて、歴史を紡いできた」

横山住職「津島の住民に慕われ続けて、歴史を紡いできたと思っているので、その思いや寺というものを、私の代では絶やしたくもなかったし、私も建てることがゴールじゃなくて、たぶん建ててからがスタートなんじゃないかなって」
横山住職「正解が何なんだろうと思いながら、模索して歩んでいるので、そんな中でも宗教者としての役目っていうのは、お亡くなりになられた方のご冥福をお祈りすることはもちろんですけど、やっぱりいまを生きてらっしゃる津島の方々の安寧を願うことと、そういった不安を少しでも和らげるのも宗教者の務めなんじゃないかなと」