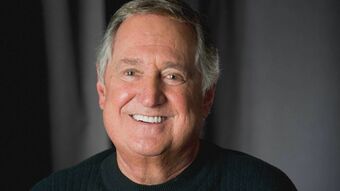医療者は「権力者である」という側面

磯野:医療者からすると、「医療者は権力者だと思われているけど、そうではない」という感覚があると思います。しかし、医療人類学の立場から、臨床現場を見たり、患者にインタビューしたりしていると、やはり医療者は権力を持っているという側面があると思います。例えば、医師の資格があったら 見ず知らずの人の裸を見ることができる。同意を得て手術すらできる。普通の人間関係ではあり得ないことが、医師の資格を媒介すると可能になる。私は、これは大きな権力だと思っています。
患者側から話を聞く機会がありますが、患者は医師にものすごく遠慮しがちです。例えば家族が入院していて、医師に何か改善を求めたり要望したりしたら、入院している家族に何か(よくないことが)起こるのではないかという不安や心配事を抱えていることもあります。
私自身も、小野寺さんがおっしゃったように、コロナ禍の感染対策はちょっとやりすぎた面が多々あったと思います。なので、新聞社のインタビューに、そうした趣旨の発言をします。その記事を自分のSNSで発信すると、必ず医療者から批判が来ます。結構な量の批判がある中で、最も多いのは「お前は現場を知らない」「お前は勉強不足だ」。この二つです。
一方で医療者に聞き取りをすると、本当に理不尽なことで、患者の家族からたたかれたりメディアからたたかれたりして、辛い思いをされています。けれどもまた逆の側面から見ると、医療者は権力を持っていて、権力を持たない人を、「お前は何も知らない」「お前は医者じゃないだろう」と、同じようにたたくという構造があったのかなというのが、私の認識です。
「あまりに目が向けられなかった」生活の現場
野路:長期戦となったコロナ禍を、人類学者の立場からはどう見ていましたか?
磯野:私は情報という観点から、このコロナ禍を見ていました。特に初期の頃は、感染してる人はほとんどいません。ごく少数でした。静岡市立静岡病院の皆さんは実際の患者をみているかもしれないけど、かかった本人でさえ、他にかかった人を見ていない状況で、人々がどうやって「コロナという病気」を知るかというと、情報を得る手段は、文字と写真と映像と音声しかないんです。それで私たちは 「静岡市立静岡病院の半径500m以内に入ったら、コロナがうつってしまう」という印象を得てしまって、それを身体感覚の中に入れ込むんです。だから「病院に近付くと怖い」となって、病院のスタッフが大変理不尽な思いをすることになる。これはつまり、病気を体で学んだのではなく、情報として病気を身につけているということです。
実は、当時私は、医療専門家の方々とは全く違う風景を見ていました。コロナ禍に入った2020年、私は失業者でした。2020年4月からハローワークに行ったんです。すると、ハローワークの開室8時半前から、外にまで行列ができていました。恐らく、アルバイトや派遣、非正規の人が、早くも解雇されていたんです。そしてハローワークの中にも外にも列を作って待っているんですね。2020年5月頃になると「密を作ってはいけない」ということで、椅子が減らされました。でもみんな、自分の番をスキップされないように、立って待っているんです。
メディアはとにかく、医療現場の画を撮りたい。病院のICU(集中治療室)の映像などです。けれど、ハローワークの行列に並んでいる人たちを撮りには、誰も来ない。すごく違和感がありました。病院の外側に、とてつもない影響を及ぼしている病気であるにも関わらず、病気そのもののリスクを出すことにばかり、メディアが集中してしまった。「不要不急」といわれて、「あれはだめだ」「これもだめだ」となった。結果、職を失い、暮らしを奪われた人がいることに、あまりにも目を向けなさすぎなのではないかという観点から、私はコロナ禍を見ていました。
決して、医療関係者が大変ではなかったとか、楽をしていると言いたいわけではないんです。ただ、多くの医療従事者の方は、あまりハローワークには行かないと思います。職業的に保障された医療従事者の立場からは、恐らく見えないだろう生活の現場があります。私はそうした現場、そうした観点から、コロナ禍というのを、医療人類学という学問の力を使って発信したいと考えていました。
野路:新型コロナに感染するかしないか、感染して生きるか死ぬかの“外周”にも、自分の仕事や命に関わるようなことがあったんですよ、という視点ですね。そうした中で、新型コロナが感染症法上の5類になるまで、感染対策が厳しく続いたことについては、磯野さんはどう考えましたか?
磯野:少し引いた目線で見ると、日本の健康をめぐる「パニックの傾向」が再び現れたといえます。とりあえず混乱を沈めるために始めた、一時的であるはずの対策が、何年間にもわたって続いてしまうという傾向です。実はこれまでも、日本では同じようなことが起こっています。
例えば「狂牛病」といわれて恐れられたBSE問題。この問題では、科学的には無意味といわれる牛の全頭検査が約10年続けられました。積極的勧奨の中止期間が長引いたHPV(子宮頸がん)ワクチンの問題も同様です。一時的であるはずの対策が科学的根拠に応じて見直されることなく、年単位でだらだら続いてしまう。不要な対策だと分かってからも、やめられない。小野寺さんがおっしゃったように、遺体を納体袋に包んで死に顔を拝むことすらできないのは、明らかにやりすぎですよね。でもそれが、今回も数年という単位で続いてしまってやめられないという、日本社会の“思考の癖”が、またコロナ禍で現れたなと思っています。